「私立の単願で早く決めて安心したい」
「でも、やっぱり都立で頑張ってほしい…」
——この時期、親の気持ちは本当に揺れますよね。
私立は助成金が増えて通いやすくなった一方で、都立受験は最後まで頑張る経験が力になる面もあります。
どちらが正解、というよりも、「この子が安心して通い続けられる高校かどうか」をいちばんに考えることが、後悔しない選び方です。
この記事では、塾講師として、そして親として見てきたリアルを交えながら、都立と私立の違いをわかりやすく整理していきます。

この記事でわかること
- 都立と私立のリアルな違い
- 子ども基準3軸のチェック法
- “12月で止まる問題”の対処
- 費用で勘違いしやすいポイント
- 学校見学の聞き方
都立か私立かで迷う背景|今なぜ揺れる?
ここ数年、私立の授業料は国と都の支援で軽くなり、単願推薦なら年内にほぼ決まるという安心感がグッと近づきました。
体調リスクや冬期講習費の心配が減るのも魅力です。
一方、都立は2月末の本番まで“学習を持続するため、入学後につながる基礎体力が残りやすいのも事実。
どちらにも良さとリスクがあります。
だからこそ、子どもが“この高校に卒業まで通い切れるか”という現実軸で見ていくのが、あとで後悔しにくい選び方です。
▷こちらの記事も参考にどうぞ
-

-
中学生の成績が悪いと都立高校はムリ? チャレンジスクール・専科・通信制まで徹底解説
続きを見る
都立第一志望のリアル|メリットと注意点

都立の良さは、まず総額コストの軽さ。
そして自由度の高い環境で、部活・行事・探究を自分で選んで動けます。
ここにハマる子は、びっくりするほど伸びます。
もう一点、見落とされがちですが、都立にも大学進学率が高い学校や指定校推薦枠が“意外と多い”学校があります。
見学で「指定校一覧」「直近の進学実績」は必ず確認を。
注意点は2つ。
- 一般入試は倍率×体調×当日の出来の影響が大きいこと。
- 自己管理が弱いタイプには自由が裏目に出ること。
朝に弱い/提出物が抜ける/言われないとやらない——が続く子は、入ってから苦戦することがあります。
▷内申点や普段の生活態度についてはこちらの記事もご覧ください
-

-
中学生の内申点を上げるには?提出物・授業態度・検定を味方にする方法
続きを見る
私立第一志望のリアル|メリットと注意点
私立の強みは、年内決定(単願)の安心と手厚い“伴走型”の仕組み。
課題・補習・面談・連絡が整備され、ルールが明確なほうが力を出せる子には相性抜群です。
設備や行事も充実していて、生活のリズムが作りやすいのもメリット。
一方で、授業料以外の費用(入学金・施設費・教材・制服・定期代・行事費など)が積み上がる点は必ず試算を。
学校のペースに合わないと、“やらされ感”で消耗することも。
単願=ゴールではありません。
合格後も学習を切らさない仕組み(入学前課題+軽い高1予習)を早めに用意しておくと安心です。
迷ったらこの3軸|性格・通学・将来像でサクッと判定

「制度や偏差値より、日々の現実」で見ると決まりやすくなります。
- 性格・学習タイプ
自由が好きで自分で計画を立て直せる子は都立向き。
“やることが明確”で伴走があると頑張れる子は私立向き。
→ 今の中学生活の“素の姿”(提出物・朝の強さ・テスト前の過ごし方)で判断するのが一番当たります。 - 通学の現実
片道時間/乗り換え/雨の日ルート/部活後の帰宅時刻。
→ 「行きたい気持ち > 通学負担」ならOK。負担が勝つなら続きません。 - 将来像・学力の地力
大学進学の意思、先取りや補習が必要か(=塾コストも含めて)。
背伸び入学なら、宿題量・小テスト頻度・定期テストの難度まで具体的に。
→ 「入学後の1学期を乗り切れる設計」になっているかで判定。
1学期でつまずいて、夏休み前に塾へ駆け込む子は毎年います。
だからこそ、いまの段階で授業ペース・宿題量・小テスト頻度まで具体的にイメージしておくのが安心。
どうしても迷うときは通学の現実を最優先に。通学がきついと、気力も体力もじわじわ削られます。
▷「部活で忙しくて勉強が後回しになりがち…」という子はこちらの記事もそうぞ
-

-
部活ばかりで勉強しない中学生は手遅れ?スポーツ推薦と内申のリアル
続きを見る
12月で止まる問題?|2月末まで走った子の“その後”
単願内定の安心は大きい一方、12月以降に勉強がゆるむと、春に基礎の穴・宿題遅延でつまずくことがあります。
逆に、都立一般で2月末まで走り切った子は、学習の持久力がそのまま高1の立ち上がりに効く場面が多いです(特に英数)。
とはいえ、これは、その子それぞれ。
推薦でも入学前課題がしっかり出る学校もありますし、合格後すぐに高1予習をコツコツ始めて伸びる子もいます。
大事なのは、“どう過ごすかの設計”。
早く決まるかどうかより、学習を切らさない生活の型を先に決めておくと安心です。
入学前ルーティンの例
- 単願:入学前課題を1日15〜20分に分解/英語は精読・音読、数学は中3の穴埋め→高1導入/就寝起床を前倒し
- 都立一般:本番までは「今日できた」を1行で可視化/試験後1週間は休息→3月2週目から高1準備を“1日10分”で再起動
学費は“授業料以外”に注意|最低限だけ正確に

私立の授業料は、国の就学支援金+都の助成で都内私立の“平均授業料相当まで”軽減されます。ただし、
- 対象は授業料のみ(入学金・施設費・教材・制服・交通費・行事費は別)
- 助成の上限は実際に支払った授業料まで
- 見直しが入ることもあるため、最新は公式で確認
この3点だけは押さえておくと、後で「聞いてなかった…」を防げます。
高校説明会で必ず聞くことリスト
雰囲気チェックで終わらせないのがコツ。数字と運用を持ち帰ると家族会議が進みます。
- 指定校推薦:一覧の有無、直近3年の実績、評定の目安
- テスト運用:平均点/赤点ライン/追試や補習の仕組み
- 提出物:遅れた時の扱い、ペナルティ
- 入学前課題:量と配布時期、推奨参考書
- 生活面:スマホ・遅刻の扱い、部活と学習の両立支援
- 費用:初年度納付金の内訳、定期代・行事費の目安
▷高校説明会についての詳しい記事はこちらでどうぞ
-
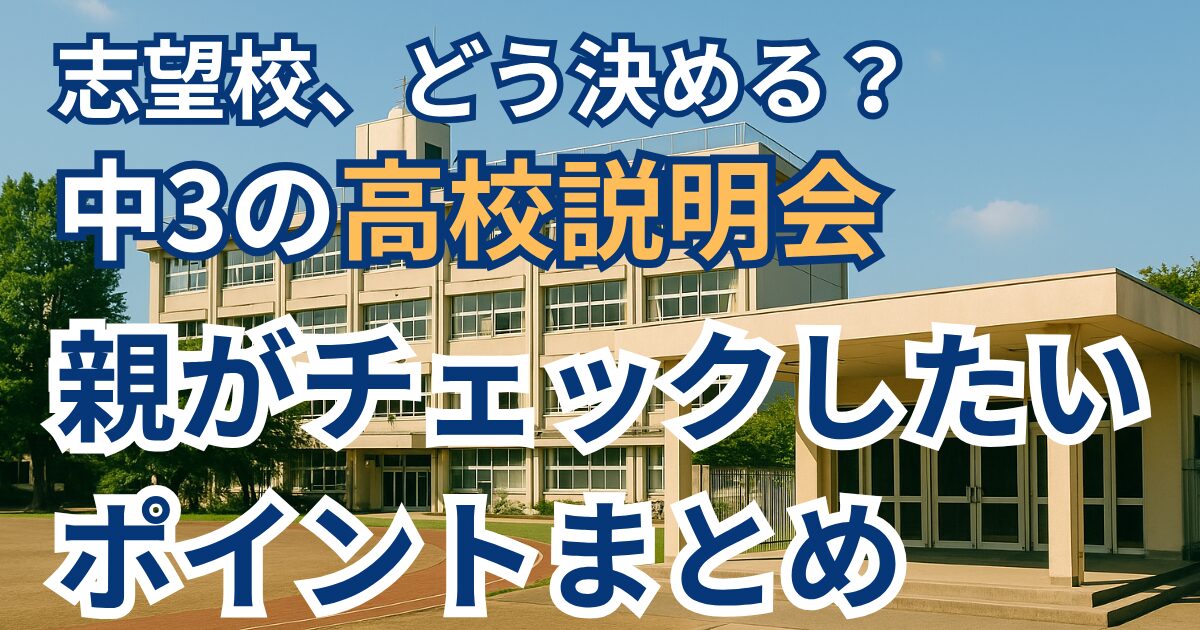
-
【中3秋】高校説明会で見るべきポイント|志望校を決める前に親が確認したこと
続きを見る

保護者からよく届く「ここが不安!」を、入学後まで見据えてやさしく短くまとめました。
Q1:大学の指定校推薦は都立にもありますか?
あります。
学校差が大きいので、一覧と近年の進学実績を必ず確認。
Q2:単願で早く決まったあと、勉強はどのくらい?
毎日15〜20分の“超ミニ習慣”でOK。
入学前課題+高1の英数を軽く先取りすると、4月の立ち上がりがラクです。
Q3:都立が本命でも、併願は必要?
おすすめします。
倍率・体調・当日の出来は読めません。
安全校を1つ用意すると、親子とも気持ちが安定します。
▷「うちの子、都立に行きたいけど学校に行けていない時期があって…」
そんな場合も、実は進学できる道はあります。
-

-
【中学生 不登校】都立高校の種類と入試方法|高校受験の選択肢まとめ
続きを見る
▷また、2026年度からの通信制高校の制度変更も見逃せません。
-

-
都立通信制高校が2026年度から“前期・後期”の2回実施に|親がまず知るべき変更点Q&A
続きを見る
まとめ|今日からできるチェックポイント
ここまでの話をサッとおさらい。迷ったら、いったんここに立ち戻ればOKです。
- 私立は年内決定の安心×伴走型。ただし授業料以外の費用は要試算
- 制度でなく“子ども基準”で選ぶ(性格・通学・将来像)
- 都立はコスト軽め×自由。「都立に行きたい」モチベが伸びの燃料に
- 12月で止まる問題に注意。合格後も学習を切らさない型を用意
- 私立の助成は授業料のみ。上限=実際支払いまで/毎年度見直し(最新は公式で)
- 見学では指定校・進学実績・テスト運用・入学前課題・費用を数字で確認
- 最終判断は「通い切れるか」。親の理想より本人の意思を尊重
進路はひとつじゃないし、合格はゴールじゃなくてスタートです。
親ができるのは、迷いを整理して、子どもが“等身大で続けられる道”を一緒に選ぶこと。
今日できるのは、たった5分の話し合いでも十分。
小さな一歩が、ちゃんと未来につながります。
