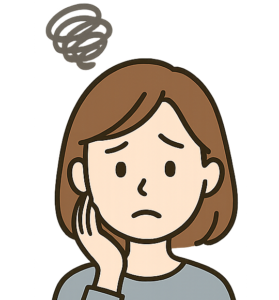
中学に入ったらまわりの子はみんな塾に行ってるみたい。
うちも塾に通わせたほうがいいのかな…?
「塾は新中1の春から通わせたほうがいいの?」
「家庭学習って何から始めればいいの?」
親も子も初めての中学生活。まわりの話に焦りながらも、どう動けばいいのかわからない…。
私も塾講師として10年以上中学生の指導をしてきましたが、
自分の子どもを受験生として見守った経験からも、“今やってよかったこと・後悔したこと”が本当に多くありました。
この記事では、塾選びや通い始めのタイミング、家庭学習の工夫まで、リアルな声をもとにお届けします。

【中1の塾はいつから?】春スタートでつまずきを防ぐ理由
私が塾で働いていて感じたのは、「できれば小6の冬休み〜中1の春休みあたりで一度通ってみるといいな」ということです。
この時期、塾によっては中学の予習をしてくれる講座があります。
中学に入る前に少しでも内容に触れておくと、4月以降の授業がぐっとラクになります。
特に算数が苦手だった子は要注意!
小学校でのつまずきがそのまま中学の数学につながってしまうことが多いので、算数で自信がないなら、中学の学習が始まる前にその苦手をつぶしておくのがベストです。
英語も同じく、「みんなスタートラインが一緒」と思われがちですが、実は小学校で英会話を習っていた子などはリスニングが得意だったりします。
ただし中学では“書く・読む・文法”が中心になるので、「単語が書けない」「文法が全然わからない」という子が、出遅れてしまうことも。
特に英単語は、書けて当然という前提でテストが作られているので、読み書きの反復が必要です。
最初は苦戦しても、練習すれば必ず覚えられるようになります。
だからこそ、塾で早めに単語練習や文法の基礎にふれておくと、その後がとてもラクなんです。
塾は“行き始めるタイミング”よりも、“どんなサポートが受けられるか”が大事。
春のうちに体験授業に行ってみたり、どんなコースがあるか調べてみるのもおすすめです。
中学生活が始まると、こんなに忙しい!

中学に入ってすぐの頃は、学校もまだ慣らし期間のような感じで、帰宅も早く「思ったより余裕があるじゃん」と思う家庭も多いと思います。
でも油断は禁物。
4月の後半くらいから、部活の仮入部や見学が始まり、帰宅時間が急に読めなくなってきます。
塾の時間と重なってしまったり、思ったより疲れてしまって勉強どころじゃない…なんて声もよく聞きます。
部活が始まってから塾を探すと、「この時間に間に合わない」「曜日が合わない」といった問題も出てきます。
塾と家庭とで話し合って、事前に仮スケジュールを組んでおくのが安心です。
また、中学生の塾の授業時間は、小学生のときよりも遅くなる傾向があります。
集団塾の場合は特に、中1でも19時スタートや21時終了といった時間帯が普通です。
それに加えて学校生活も本格化してくると、寝るのが遅くなってしまい、翌朝つらそうにしている…というのはあるあるです。
できれば、入学後しばらくは「早く寝る」を大事にしてあげてほしいと思います。
夜遅い塾に通わせる場合でも、なるべく帰宅後すぐにお風呂→寝る流れを作っておくとリズムが整います。
中学生活のペースに慣れるまでは、親が少しリードして「寝る時間・ごはん・塾」の調整をしてあげるのがとても大事。
勉強ができるかどうか以前に、まず“生活できるかどうか”がカギなんです。
やる気がないように見える子が実は…?
【集団塾vs個別】新中1に合う塾タイプの選び方と注意点

塾のスタイルによって、通塾タイミングやペースはかなり変わります。
特に“集団塾”と“個別指導”では、スタートの時期や時間帯に違いが出やすいです。
集団塾では、中学の授業に合わせたカリキュラムで進むため、基本的には「通年型」。
つまり、4月からいきなり“本番”が始まります。
多くの集団塾では、4月から部活後の19時〜21時など、かなり遅めの時間帯に設定されており、「小学生の延長」ではなく、いきなり中学生モードになります。
そのため、部活の仮入部や見学がある時期は、帰宅が塾に間に合わないことも。
これを知らずに「とりあえず集団塾に…」と入ると、予定通りに通えずリズムが崩れることがあります。
一方、個別指導の塾は、比較的柔軟にスケジュールを調整できます。
中1の4月は仮スケジュールで様子を見つつ、5月以降に部活が確定してから正式な通塾曜日・時間を決める、という進め方も可能です。
集団塾にも個別指導にも、それぞれメリット・デメリットがありますが、「うちの子にはどちらが合いそうか」「生活リズムに無理がないか」は、入塾前にしっかり見ておくと安心です。
また、塾と保護者がこまめに連絡を取れるかどうかも大事なポイント。
特に最初のうちは、通えるかどうかの確認や、部活との兼ね合いの相談ができる雰囲気かどうかも見ておくと良いと思います。
集団塾と個別指導、それぞれの特徴や選び方について詳しく知りたい方は、こちらの記事がおすすめ
「様子を見てから」派の落とし穴
「まずは中学生活に慣れてから。塾は1学期の様子を見てから考えよう」
これはよくある考え方で、もちろん間違ってはいません。
でも実際には、1学期の通知表が出てから「あれ…思っていたより成績が低い!」と驚いて、夏休みに慌てて塾を探す家庭も多いのです。
しかも、多くの子が「わからないまま夏を迎える」のではなく、「小学校の内容が十分に理解できていなかった」という状態で中学に入っていることが多く、1学期に入ってからではすでに復習が手遅れになっているケースもあります。
だからこそ、できれば“様子見”の期間を短くして、気になることがあれば早めに動いてあげるのが大切です。
もちろん、子どもの性格によっては、環境に慣れるのに時間がかかるタイプもいます。
その場合は、塾に通わせる・通わせないというよりも、「家庭での勉強習慣がついているか」「つまずきを見つけたときにすぐ対応できる体制があるか」を意識しておくとよいと思います。
塾がすべてではないけれど、「あとで焦る」よりは「先に準備しておく」方が、結果的には子どもも親もラクになります。
塾に行かない選択肢と、家庭学習で大切なこと

「うちは塾にはまだ通わせない予定」「金銭的に塾は中3から…」というご家庭ももちろんあります。
それは決して悪いことではありません。
ただ、その場合に気をつけたいのは、「子ども任せにしない」ということ。
中学生になったからといって、すべてを本人にまかせてしまうのはかなりハードルが高いです。
中学校の勉強は、小学校よりも一気に量が増え、複雑になります。
それに加えてスマホやゲーム、SNSなどの誘惑も増える中で、1人で計画を立てて実行していくのは、大人でも難しいことです。
だからこそ、塾に行かないなら、なおさら家庭でのサポートが必要。
- 勉強する時間帯を決めておく(例:夕飯前に30分など)
- 音読や計算など、日々のルーティンを決めて一緒に取り組む
- 英単語をテスト形式でチェックしてあげる
- 問題集を親が開いて「今日はここまでやろうか」と声かけする
このようなちょっとした関わりだけでも、子どもにとっては“やる気のきっかけ”になります。
そして、塾に行かないことで時間的・金銭的に余裕ができるなら、その分「親が手間をかける」ことで十分にフォローできます。
実際、うちも家庭学習中心で受験を乗り越えた経験があります。
家庭学習だからこそ、「無理せず、でも続けられるスタイル」を見つけることが大切です。
家庭学習の管理ってどうすれば?という方はこの記事もぜひ
くわしい教材の選び方はこちらにまとめてます!
塾に通う?通わない?子どもに合ったスタートを考える
中学校のスタートは、親も子どもも初めてのことばかりで戸惑うもの。
「塾はまだ早い?」「家庭学習って必要?」と悩むこともたくさんあります。
でも大切なのは、周りと比べることではなく、“自分の子に今必要なサポート”を見極めること。
塾に通わせるなら早めにスケジュールや生活リズムを整える。 通わせないなら、家庭でどう支えていくかをしっかり考える。
どちらの選択でも、親が「ちょっと先回りして考える」だけで、子どもがラクになる場面はたくさんあります。
がんばりすぎず、でも見逃さず。
新生活を応援する気持ちで、寄り添っていけたらいいですね。




