冬休みは、いよいよ入試本番までの最終調整期間。
でも「この時期って何をやればいいの?」「もう間に合わないのでは…?」と焦るご家庭も多いのではないでしょうか。
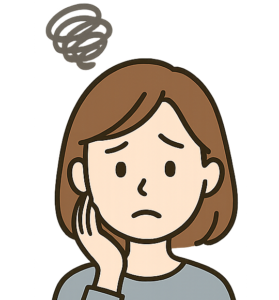
気持ちばっかり焦っちゃって何していいのかわからない…
かといって親が口出してもしょうがないかもだし…
都立高校入試の勉強は、「冬休み~入試直前期」にかけての過ごし方がカギ。
この期間は、がむしゃらに勉強量を増やすよりも、「どのレベルの問題を、どれだけ確実に取るか」という冷静な戦略が何より大切です。
今回は、塾講師として、そして受験生の母として見てきた経験をもとに、
冬休みから直前期にかけて各教科でどんな勉強をすれば点が安定するのかを詳しく解説します。
▷まずは、都立入試の得点配分や内申の仕組みを知っておくと、冬の勉強計画が立てやすくなります
-
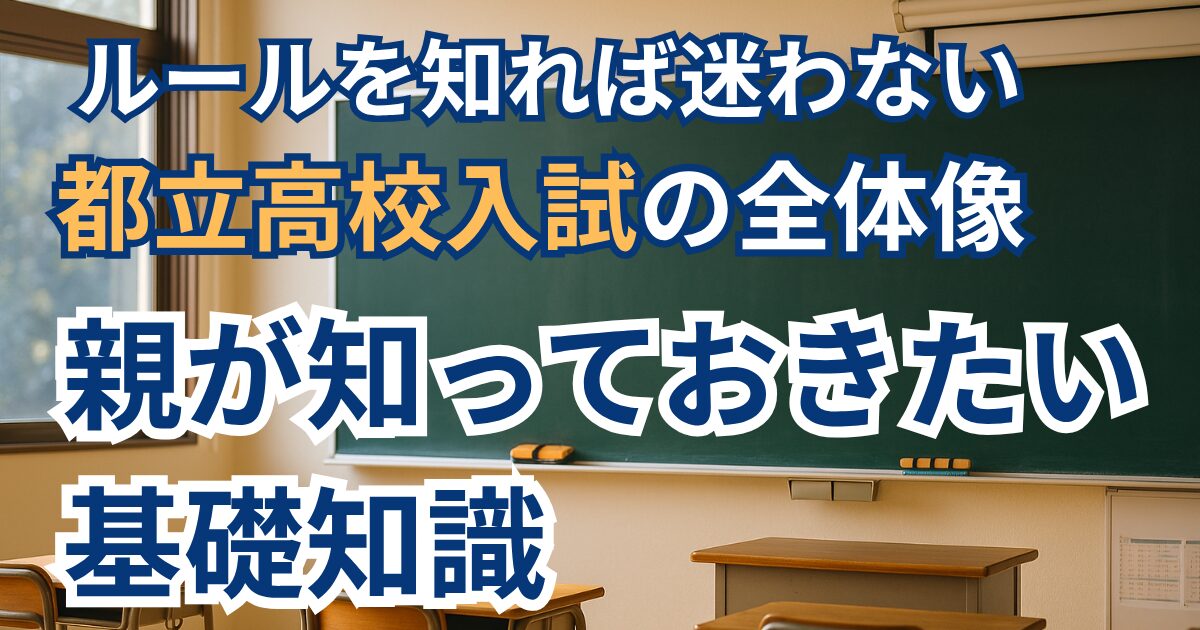
-
【都立高校入試の仕組み】内申点・学力検査・推薦の流れをやさしく整理|親が知っておきたい基礎知識
続きを見る

この記事でわかること
- 都立高校入試に向けた「冬休み〜直前期」の勉強の考え方
- 各教科(数学・英語・国語・理科・社会)の重点ポイント
- 「落としてはいけない問題」を確実に取る勉強法
- 親ができる声かけ・サポートのヒント
- 家庭でもできるAI活用&市販教材の取り入れ方
都立高校入試に向けた冬休み勉強の基本方針
塾講師として、そして受験生の母として見てきた経験から言えるのは、冬休みこそ「落としてはいけない問題を落とさない」勉強に集中すべきだということ。
この“土台”をどれだけ固められるかが、最終的な得点力を決めます。
▷塾をどうするか迷っている方はこちら
-

-
冬期講習、うちは受ける?受けない?|塾講師ママが本音で語る“やらない選択”と家庭でできる冬の勉強
続きを見る
「落としてはいけない問題」を確実に取る
都立入試では、難問に手を出すよりも、みんなが取れている問題を確実に取ることが何より大事です。
つまり「当たり前のことを確実にできる力」を積み上げること。
たとえば、合格に必要な点数が300点(5教科×60点)だとします。
その60点を取るためにまず必要なのは、難問ではなく基本問題の精度です。
計算・語彙・基本用語・リスニングなど、“毎日やれば必ず取れる問題”を積み重ねていくことが、合格のいちばんの近道です。
点の積み上げ方を戦略的に考える
もし目標が400点のように高い場合でも、考え方は同じです。
まず300点(=基礎の積み上げ)を確実に固め、残り100点を「少し難しい問題」で積み上げていきます。
1教科あたりで考えると、
まず50~60点を落とさない → プラス20点を狙う。
この「プラス20点」を取るには、
- わからない問題を放置せず、YouTubeや解説動画で確認する
- 学校や塾の先生に質問して理解を深める
- 過去問の解説を丁寧に読む
といった“自分から理解を取りに行く姿勢”が大切です。
この一歩が、点数の底上げにつながります。
「できない問題」に執着しすぎない勇気
入試では、100点のうち正答率がとても低い超難問が含まれていることもあります。
みんなが落としている問題に悩むより、“みんなが取れている問題を確実に取る”ことを意識しましょう。
「ここができないどうしよう」と焦るよりも、
「80点分を取り切る」と気持ちを切り替えるほうが、結果的に安定します。
そのためにも、Vもぎなどの模試を活用して、
- 自分が取りこぼしている“みんなが取れている問題”を見つける
- そこを確実に取れるように復習する
という視点が欠かせません。
都立入試は、冷静な戦略と基礎的な土台で勝負が決まります。
冬休みは「勉強量を増やす期間」ではなく、“取れる問題を取り切る力”を磨く期間。
ここを意識するだけで、冬の勉強の質がぐっと変わります。
▷Vもぎ受験の仕方についてはこちらの記事で
-
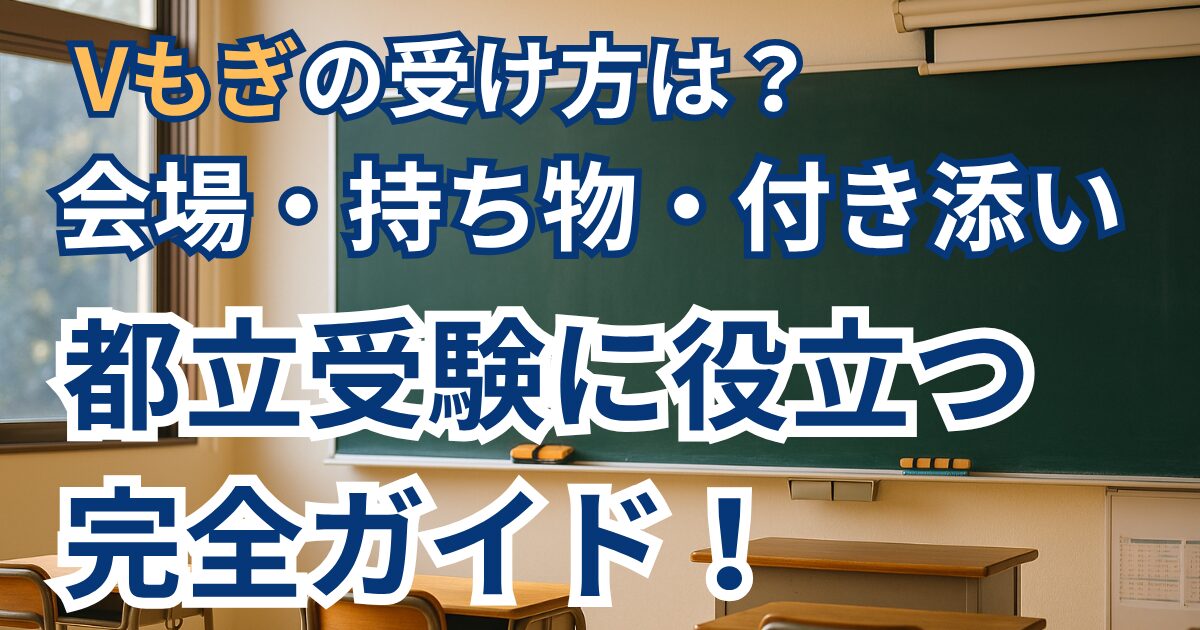
-
【Vもぎ】親は一緒に行く?受け方・会場選び・何回受けるかまで体験談で解説
続きを見る
【数学】毎日10分で“計算スピードと正確さ”を固める

都立入試の数学でいちばん大切なのは、計算スピードと正確さです。
どんなに応用問題が解けても、計算でミスをすれば得点は伸びません。
逆に、計算がしっかりしていれば、計算問題や小問集合で安定して得点できます。
まずはここを取り切れるだけで、全体の点がぐっと安定します。
「土台=計算力」は、最後まで伸ばせる
塾では冬になると、応用問題や実戦演習に比重が移ります。
でも実際には、土台の計算力がまだ安定していない子がかなり多いです。
先生側も「この時期に計算練習なんてもういらないでしょ」と思いがちですが、私はむしろ、ここからこそ毎日10分でいいから計算練習を続けてほしいと感じています。
これは偏差値64の都立に合格したうちの長女も同じ。
入試直前まで毎日、計算のみの問題集を1〜2ページずつやっていました。
派手さはないけれど、「当たり前の計算を当たり前に正確にやる」ことで、本番でも焦らず点を積み上げられます。
毎日の練習方法(家庭でもできる)
塾に通っていない子でも、次のようなやり方で十分効果があります。
- 都立過去問の大問1だけを時間を計って解く(5分目安)
→ 間違えた計算パターンをノートにメモ。翌日にもう一度やる。 - 正負の数・文字式・方程式の計算を毎日1ページずつ
→ 学校ワークや市販の基礎問題集(「ひとつひとつわかりやすく」など)でOK。 - 1週間ごとに“自分の弱点計算”を振り返る
→ 割り算でミスが多いのか、符号の混乱か、意識して直す。
時間は10〜15分で十分。
“毎日やる”ことがポイントです。
ここができれば都立の数学は安定する
計算力が身につくと、次のような問題にも対応しやすくなります。
- 一次関数の式を求める問題
- 作図・角度・面積・体積などの図形問題
- 確率の基本パターン
つまり、「計算が速く・正確にできる」ことは、応用力を支えるベースでもあるんです。
応用問題に取り組む前に、まずは基礎の土台を完璧にしておく。
それが結果的に、70点・80点を狙う力にもつながります。
親のサポートポイント
- 計算練習の時間を“毎日のルーティン”に入れてあげる(朝・夜など)
- ミスが多くても責める言葉は言わない
- 正解したときはしっかり褒めて、「正確さ」を認めてあげる
勉強量よりも、“集中して10分を積み重ねる”ことが大事。
「やる気が出ない日でも、10分だけやってみようか」くらいの軽さで続けていければOKです。
▷こちらの記事で、自分のペースで進めやすい教材を紹介しています
-

-
【中学生の家庭学習】レベル別おすすめ問題集と効果的な使い方ガイド
続きを見る
【英語】“文法より書ける・読める”で確実に得点する
都立入試の英語は、他の教科に比べても「基礎力」がそのまま点数に出ます。
文法問題はほとんど出題されないので、難しいルールを覚え直すより、“書ける・読める力”を整えることが最優先。
特に、英作文と長文読解の2つは得点差がつきやすく、「そこそこ書ける」「なんとなく読める」レベルを“確実に得点できるレベル”まで引き上げることが、冬休み〜直前期のテーマです。
まずは“英作文”で12点を確実に取る
都立の英作文は、毎年200字作文と同じように「型」を覚えれば安定して点が取れます。
満点を狙う必要はありません。10点前後を取りに行くのが現実的な目標です。
- 基本構成を覚える:「自分の意見 → 理由 → まとめ」
- 難しい単語を使わない:“study”“like”“because”など中1レベルでOK
- スペル・文法ミスを減らす:正確に書く方が高評価
I think studying English is important.
Because we can talk with many people.
So I want to study English more.
↑こんなシンプルな文で十分なんです。
「文法的にきれいか」よりも、「自分の意見を正しく伝えられるか」が評価されます。
もし書くのが苦手なら、自分の意見を日本語でメモしてから英文に直す練習を。
1日1題だけでも、「型にそって書く習慣」をつけることが大切です。
長文読解は“完璧に読む”より、“拾って取る”練習を
長文は苦手な子が多いですが、都立の問題は部分的に理解しても得点できる構成になっています。
全文を訳そうとせず、「設問の答えを探す読み方」に切り替えましょう。
- まずは設問(問題文)を先に読む
- 何を聞かれているか意識して本文を読む
- 選択肢問題は「本文中の似た表現」を探す
これだけでも点の取り方が変わります。
冬休み中に過去問を3年分だけでもこの方法で練習しておくと、
“長文アレルギー”がぐっと減ります。
単語力は「計算と同じ」——毎日の積み重ねでしか身につかない
単語を覚えるのは地味だけど、いちばん裏切らない勉強です。
計算練習と同じで、コツコツ続けることがすべて。
- 1日10〜20語でもいいから“毎日触れる”
- 書いて覚えるより、“声に出して読む”方が定着しやすい
- 教科書や過去問の中で出てきた単語を中心に
特に都立は、教科書レベルの単語を正しく理解できているかが問われます。
難しい単語を無理に覚えるより、「知ってる単語を正確に読める・使える」ことを優先しましょう。
親のサポートポイント
- 単語カードやアプリを使う時間を“毎日のルーティン”に入れる
- ChatGPTなどで英作文のミスをチェックしてあげる
- "取り組めたこと"や“書けたこと”を褒める
英語は結果が出るまで時間がかかる教科。
でも、1日10分でも“積み重ねた人だけが伸びる”教科です。
この冬は「英語=毎日少しでも触れる」を合言葉に、焦らず地道に続けていきましょう。
▷勉強しやすい部屋づくりについては、あったか勉強グッズ」も参考になります。
-

-
【中学生の集中力を上げる!】冬にほんとに役立った“あったか勉強グッズ”おすすめ
続きを見る
【国語】漢字と作文で差をつける!家庭でもできるAI活用法

都立入試の国語は、他教科と比べて全体の難易度がやや低め。
記号選択が多く、平均点も高い年が続いています。
そのぶん、差がつくのは確実に取れる2つのパート——「漢字」と「作文」です。
漢字は“過去問中心”で反復あるのみ
漢字は毎年ほぼ同じレベル・分野から出題され、実は過去問から同じ漢字が出題されることも。
「読む・書く」どちらも中学3年間の教科書レベルで十分です。
- 過去問3〜5年分の漢字を繰り返し解く
- 間違えた漢字は専用ノートにまとめておく
- 「送りがな」「意味の違い」も一緒にチェック
この3ステップを冬休み〜2月まで続ければ、20点前後は安定して確保できます。
作文は“時間内に200字書ける”練習を
都立入試の作文は、200字以内で自分の意見を書く形式。
ここで差がつくのは、「深い考察」などよりも“設問に沿った内容のものを時間内に書ききれるか”どうかです。
書けば書くほど上達するので、
- 1日1題、過去問や予想テーマで書く
- 書いたあとに「意見→理由①→理由②→まとめ」になっているかチェック
- できれば誰かに読んでもらう
このサイクルを冬のうちに作っておくと、本番で落ち着いて書けます。
塾に通っていなくても“AI添削”で練習できる!
作文の練習で悩むのは「誰に添削してもらえばいいの?」という点ですが、いまはChatGPTなどのAIツールを活用する方法もあります。
たとえばこんな指示を出すと、かなり都立入試に近い形で添削してもらえます👇
「都立高校入試の200字作文の採点基準に近い形で、
内容・構成・語彙・文法の4観点でコメントしてください。
改善点と良かった点の両方を教えてください。」
これで、内容のズレや文のつながり方、語彙の使い方まで丁寧に指摘してもらえます。
無料版でも十分活用できるので、塾に行かなくても“書いて→直して→また書く”練習が可能。
英作文も同様に、文法やスペルチェックはAIが得意分野なので、
冬の勉強にAIを取り入れることで「自分で練習できる力」がつきます。
まとめ|国語は「落とさない問題」を確実に
都立の国語は、漢字・作文で“確実に取ることで6〜7割を狙えます。
苦手だからといって全体を避けるより、できる部分に集中するほうが点が伸びる教科。
漢字+作文でまとまった得点源を作るつもりで、冬の間にコツコツ練習していきましょう。
【理科・社会】詰め込みより“整理と反復”で安定させよう
理科と社会は、「冬休みに全部やり直そう!」と思うと終わりません。
ここは、新しいことを覚えるより“抜けている基本”を整理して固めるのがコツです。
理科のポイント
- 「覚えてたのに出てこない」を減らすのが第一目標。
- 教科書やノートをパラパラ見返し、「説明できない用語」にマークをつけて確認。
- 過去問や模試で間違えた問題を、分野別(生物・化学・物理・地学)にノートまとめ。
- グラフ・実験・図の問題は、解答根拠を「なぜそうなるか」まで説明できるように。
社会のポイント
- 地理・歴史・公民を“全部”やろうとせず、苦手分野を重点的に復習。
- 特に地理は統計・資料問題、歴史は時代の流れ、公民は言葉の意味を意識。
- 一問一答で覚えるだけでなく、「どんな問題で出るか」を過去問で確認。
- ニュースや身近な話題と結びつけて覚えると定着しやすい。
どちらも、冬〜2月は「過去問の見直し+基本の暗記」が最優先。
新しい問題集に手を出すより、“覚えたことを忘れない工夫”に時間を使いましょう。
▷暗記に役立つ勉強グッズは、こちらの記事でまとめています。
-

-
中学生の勉強がはかどる!本当に使えるおすすめ勉強グッズ8選
続きを見る
まとめ|冬休み〜直前期は“落とさない勉強”で合格をつかむ

冬休み〜2月にかけては、「何をどれだけやるか」よりも、「どの問題を確実に取れるようにするか」が勝負を分けます。
この記事で紹介したポイントをおさらいすると――
- 数学: 計算練習を毎日10分。土台を固める。
- 英語: 英作文と単語の積み重ねで“書ける・読める力”を。
- 国語: 漢字+作文で確実に取れる20点を確保。
- 理社: 新しい知識より、過去問復習と基本の整理。
どの教科も「満点を取る勉強」ではなく、“落とさない問題を落とさない”勉強を徹底すること。
ここを意識するだけで、都立入試はぐっと安定します。
最後の1〜2か月、焦る気持ちはみんな同じ。
でも、焦って新しいことに手を出すより、今ある力を磨くほうが伸びやすい。
冬休み〜直前期は、親子で一緒に「取れる問題を取り切る力」を育てていきましょう。

受験までの毎日を、焦らず、コツコツ、地道に。
それがいちばん強い“冬の戦略”です。
▷「うちも家庭で教材を使ってみようかな」という方は、こちらもどうぞ
-

-
【中学生の家庭学習】レベル別おすすめ問題集と効果的な使い方ガイド
続きを見る
