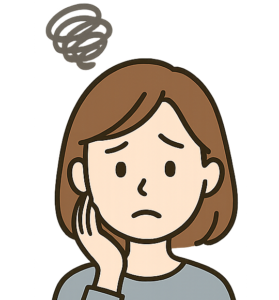
中学生の息子、通知表で3は多いんだけど、なかなか4にならなくて…
「うちの子、いつも通知表がオール3…」
「頑張ってるのに、なかなか4がつかない」
そんな親の声、よく聞きます。
今の中学校の成績は“絶対評価”。
昔のような「3=普通」「5=すごく優秀」というイメージとは違い、 今は「3」がかなり広い層に当たります。
実際、テストの点が50点でも3がつくこともあれば、 70点台後半を取っても3がつく…ということも。
つまり、「3→4」は思っている以上にハードルが高い!
でも、正しい家庭学習と親のちょっとしたサポートがあれば、 それは十分に狙えるステップなんです。
この記事では、
- 成績「3」のリアルな実態
- 「4」を目指すための勉強の考え方
- 数学・英語を中心とした教科別の家庭サポート術
を、塾講師&母の視点から詳しく解説します!

成績「3」はこんなに幅広い!知られざる通知表のリアル
中学校の成績は「絶対評価」でつけられています。
これは、周りと比べてではなく「その子がどれだけ到達しているか」を見る制度。
とはいえ、実際には「3」の幅がとにかく広い!
- テストで50点台でも3がつく子
- 提出物や授業態度でギリギリ3をもらっている子
- 逆に80点近く取っても3がつく子
…と、同じ「3」でもレベル感はバラバラ。
実感として、「1」はほぼつかないので、 2〜3=下位層、4〜5=上位層という分類になり、 「3」は中間というより“ちょっと頑張りたい層”なのです。
つまり「3→4」は、偏差値でいえば45から50あたりへのジャンプ。
なんとなく3がついている子を、地力のある3に変えていくことが必要になります。
▷定期テストへの取り組み方はこちらの記事で
-

-
テスト勉強の仕方がわからない中学生に親ができること|今すぐ使える教科別対策
続きを見る
「3→4」に必要な力と考え方とは?

4を取るには、主に次の3つの要素が安定して高水準であることが求められます。
- テストの点数(定期テストで80点前後)
- 提出物の充実度・提出率(丁寧に・期日内に)
- 授業態度・参加意欲(発言・ノート・聞く姿勢)
このうちどれかが大きく欠けると、たとえ理解できていても「4」はつきにくい。
とくに都立高校入試では、内申点が大きく影響します。
求められているのは、「テストが取れるだけの子」ではなく、「オールマイティーに努力できる子」。
そのためにも、まずは「3」の中でもしっかり地力をつけて、 そこから4を目指すステップを踏んでいく必要があります。
教科別!「成績3」から脱出する家庭学習サポート術
ここでは、特に差がつきやすい数学と英語にしぼって、 「3」から「4」に近づくための家庭学習のポイントを紹介します。
▷おすすめの教材はこちら
-

-
【中学生の家庭学習】レベル別おすすめ問題集と効果的な使い方ガイド
続きを見る
数学|基礎力+ケアレスミス対策がカギ
「なんとなく3が取れている」数学の成績。
その中身を見てみると、計算ミスが多かったり、基本的な解き方を理解しないまま進んできたパターンが目立ちます。
- 本人は「だいたい解けてる」と思っているが、実は途中式があやふや
- 計算方法が自己流で、根本的に理解できていない部分がある
- 応用よりも、基本問題の正確さに課題がある
このような場合、まずは途中式をしっかり書かせることが第一歩。 その中で誤った手順や理解のズレに気づくことができます。
- 計算や基本問題での取りこぼしをなくす
- 応用よりも「確実に正解する力」をまずつける
- 基本的なやり方を定着させる
少し時間はかかりますが、可能なら1年生の計算範囲から総ざらいするのがおすすめ。
▷計算ミスを防ぐポイントはこちらの記事で
-

-
【中1数学】計算ミスを防ぐ!家庭でできるサポート術
続きを見る
英語|文法理解+単語の定着
今の中学校の英語は、授業で文法を深く扱わないことも多く、 ディスカッションやスピーチなど“実践型”が中心になっています。
でもテストでは、文法・語順・書き換え問題などがしっかり出ることも多いため、 家庭での文法フォローが必要不可欠。
▷中2英文法の注意点はこちら
-

-
中2英語で点数が伸びない?テストによく出る「助動詞・接続詞」を親子でやさしくおさらい!
続きを見る
また、英検を目標にすると、単語や文法の定着にハリが出るご家庭も多いです。
▷英検合格体験記はこちら
-

-
中3で英検準2級に合格!1学期に受けてよかった理由と勉強スケジュール
続きを見る
「テストは取れるのに3」のパターンはここを見直そう

よくあるのが、「テストで80点取ったのに、通知表は3でした…」 というケース。
これは、提出物や授業態度が影響していることがほとんどです。
- ノートが未提出/乱雑/期限を守れていない
- 授業中の姿勢が悪い(寝ている・スマホ・私語など)
- 学校行事や課題で消極的な態度が目立つ
中でも男子に多いのが、「理解できているのにやらない」パターン。
先生は成績を「総合的に判断」しているので、 “テストの点だけでは評価されない”ということを、親子で共有しておくと◎です。
▷提出物についての詳しい内容はこちら
-

-
提出物を出さない中学生に悩む親へ!怒らずできた3つのサポート法
続きを見る
親にできるのは「整えること」と「励ますこと」
「教える」ことが親の役割だと思いがちですが、 本当に大事なのは、“学べる環境を整えてあげること”。
- テスト前に一緒にスケジュールを立てる
- 必要な教材を用意しておく
- 提出物の進捗を一緒に確認する
- 小さな努力をほめる
このような「勉強しやすい空気」をつくることが、 子どもにとっては何よりのサポートになります。
あなたの関わり方が、きっと子どもの背中を押してくれます!
