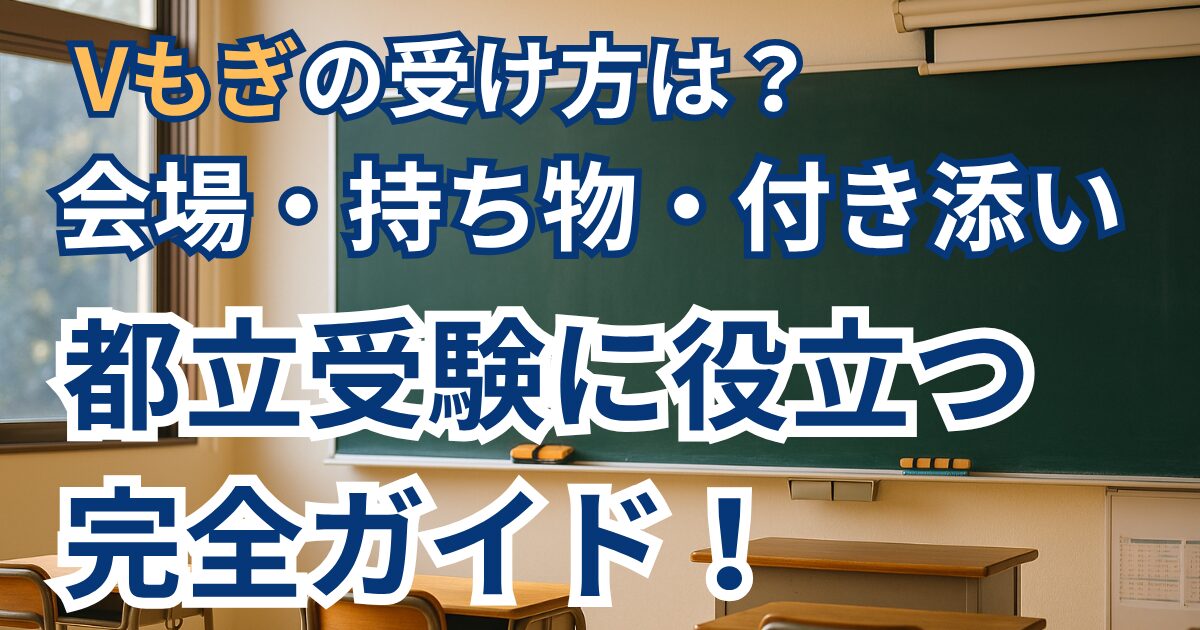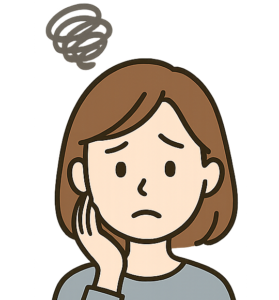
中学校の担任から「必ず『Vもぎ』を受けてください」って言われたんだけど、
それってホントに受けるべきなの?申込み方もよくわからないし…
中3になると塾や学校から「模試を受けましょう」と言われる機会が増えてきます。
でも実際、模試をどうやって受けるのがベストなのか、よくわからないという方も多いのでは?
この記事では、「Vもぎ(V模擬)の受け方や会場選び、親は一緒に行くべきか?」 という不安を持つご家庭に向けて、実際にVもぎを受けた私の娘の体験をもとに、模試の受け方・会場の選び方・活用のポイントをお伝えします!

この記事でわかること
- Vもぎの受験当日の流れと持ち物
- 親は一緒に行くべきか・送迎の注意点
- 会場選びと申込方法のポイント
- 何回受けるのがベストか
- 判定結果の見方と復習のコツ
Vもぎを受ける目的と申し込み方法
Vもぎはなぜ受けるべきなのか、そして実際の申し込み方法について紹介します。
中3で模試を受ける理由とは?
模試を受ける目的はズバリ、「現在の実力を把握すること」と「入試本番に向けたシミュレーション」の2つです。
特に都立高校のように倍率が高く、1問で合否が分かれる入試では、模試での経験が大きな力になります。
初めて模試を受けたときは、時間配分に失敗したり、緊張で頭が真っ白になったり……。
でも、何度か受けるうちに「ペース配分」「集中力の持続」「会場の雰囲気」にも慣れていきます。
練習だからこそ、失敗できる。
これが模試の大きな価値です。
▷受験勉強と並行して英検にもチャレンジ
-

-
中3で英検準2級に合格!1学期に受けてよかった理由と勉強スケジュール
続きを見る
Vもぎの申し込み方法と注意点
個人で申し込む場合、申し込みは進学研究会の公式サイトから行います。
受験会場は「先着順」ではなく、各回ごとの申込期間内で受け付ける方式なので、焦らず期間内に申し込みましょう。
ただし、会場は希望通りにならない場合もあるので、申し込んだあとはマイページや受験票で、会場の確定情報を必ず確認するのが大事!
Vもぎの受験料は通常1回4,900円(税込)ですが、3回以上まとめて申し込むと1回4,500円(税込)になります。
1回あたり400円の差があるので、何度か受ける予定があるなら回数券がおすすめです。
しかも、3回分だけ買っておけば、あとから1回ずつ追加することもOK。
例:最初に3回分を購入 → 後日もう1回だけ追加購入 → 合計4回分で受験できる!
「全部で何回受けるか決めてない…」という人にも使いやすい仕組みです。
Vもぎは何回受ける?おすすめの受験回数とタイミング

Vもぎを受けるにあたって、いつから・どのくらいの頻度で受けるのがいいのか、悩む人も多いですよね。
わが家の体験をふまえて、模試の時期と内容の関係、受け方のコツをご紹介します。
模試の回数は「月1ペース+ラスト1回」がベスト!
塾では、Vもぎが“必須模試”として設定されていることが多く、私の勤める塾でも中3の9月~1月で7回ほど受験していました。
月に1〜2回のペースですね。
ただ、高校の学校説明会などと時期が重なり、スケジュールがハードで、正直「こんなに必要かな?」と思うことも。
特に9月〜11月の模試は、数学の「三平方の定理」などの未習内容がまだ模試に入っていないため、実力が正確に反映されにくい場合もあります。
そのため、12月・1月の模試が“本番に近い内容”であり特に重要。
ラストの模試は1月第2週あたりで受けておくと、結果を最終確認しやすくおすすめです。
▶おすすめの受験ペース:
- 9月〜1月の5ヶ月間で、月1回ペース(計5回)
- 入試直前の1月に必ず、仕上げとして受験
無理なく実力を測るには、このくらいのペースがちょうどよかったと感じました。
Vもぎはどこで受ける?会場選びと申込方法

模試は会場によって緊張感が変わるもの。
志望校の雰囲気を知る機会にもなるため、会場選びは意外と重要なポイントです。
塾からの申込と個人申込の違い|親はどっちを選ぶ?
塾経由で申し込む場合は、会場や日程を塾側が一括で管理してくれるため手続きがラクです。
ただし、会場の選択肢は限られる場合もあるので注意しましょう。
個人で申し込む場合は、希望する日程や会場を自由に選べます。
ただし受験会場は先着順ではなく、各回ごとの申込期間内で受け付けられる方式です。
焦らず、申込期間を確認して手続きを行いましょう。
「Vもぎはどこで受けるのがいい?」と迷う方は、志望校の会場を体験したいか、アクセスの便利さを重視するかで考えるとよいです。
模試会場は主に私立高校が使用されており、志望校の雰囲気を体感したいという目的で選ぶのもおすすめです。
ただし、休日の模試と平日の入試では交通事情が異なるため、通学経路の確認は過信しすぎないようにしましょう。
一方で、模試会場をあえて志望校とは別の場所にして、「知らない場所で受験する緊張感に慣れる」ことを重視するのもひとつの考え方。
どこで受けるかを工夫することで、より実戦的な練習になります。
▷志望校の雰囲気が気になる人は、見学の体験記も参考に
-

-
【体験記】高校見学で“見ておいてよかったこと・失敗したこと”を学年別に解説!
続きを見る
Vもぎ当日の流れと持ち物|親のサポート体験談
初めての模試では「親は一緒に行った方がいいの?」と迷う方も多いです。
基本は子どもだけで受験しますが、送迎や会場付近までの付き添いは、注意点を守れば可能です。
わが家でも送迎をした経験があります。
模試当日は、朝早くから始まり、昼過ぎまでかかる長丁場。
集中力が必要になるため、親のちょっとしたサポートが力になります。
スケジュールと注意点|朝早く集合、昼食はなし
受付は朝7時45分から始まります。
8時20分から志望校カードの記入が始まり、回収後の8時40分から試験開始です。
最後の教科は13時30分に終了し、その後順次解散となります。
校舎を出るのは14時前になることもありました。
休み時間中に水分補給はできますが、お菓子や食事はNG。
昼休憩がないため、途中でお腹が空いて集中力が切れてしまう子も多いです。
わが家では、娘にブドウ糖を持たせていました。
本番の入試でも役立ったアイテムで、手軽に口に入れられ、見た目もお菓子っぽくないので便利でした。
車の送迎は禁止されている
娘の模試では、友だちと一緒に親が送迎をしていたこともありました。
ただし、会場周辺への車の乗り入れは禁止されているため、会場から離れたコインパーキングなどに停めて、そこから徒歩で送る必要があります。
それでも、行きの電車の負担を減らせたり、帰り道にすぐ模試の見直しができたりと、送迎してよかったと感じる場面も多くありました。
「模試をがんばるのは子ども。でも、せめて行き帰りくらいは快適に」
そんな思いで、わが家なりにできる範囲のサポートを心がけていました。
「Vもぎは親と一緒に行くべき?」という問いに対しては、基本は子どもだけで十分。
ただ、送迎はサポートとして効果的でした。
Vもぎ結果の見方と志望校判定の活用法
模試を受けたら、結果をどう活かすかが超重要!
A判定にこだわりすぎず、模試をうまく活用していきましょう。
成績の推移をチェック
大切なのは1回ごとの結果ではなく 成績の推移 です。
特に10〜11月は、まだ中3の範囲がすべて終わっていないことが多く、実力が十分に反映されない時期。
12月〜1月の模試こそ、本番に近い内容になるので、その時期の判定を重視するのがおすすめです。
模試の判定は志望校選びの判断材料に
Vもぎの判定は信頼性が高いとされており、特に12月や1月の模試でA判定以上が出ていれば、合格の可能性は十分あると言われます。
逆に、最後までC判定以下だった場合は、受験校の見直しも視野に 入れたほうがいいかもしれません(特に都立一本で私立の併願がない場合)。
模試の判定は「合否そのもの」ではありませんが、冷静に進路を考えるための大切な材料です。
▷判定結果を見て志望校選びに迷う場合はこちらの記事をどうぞ
-
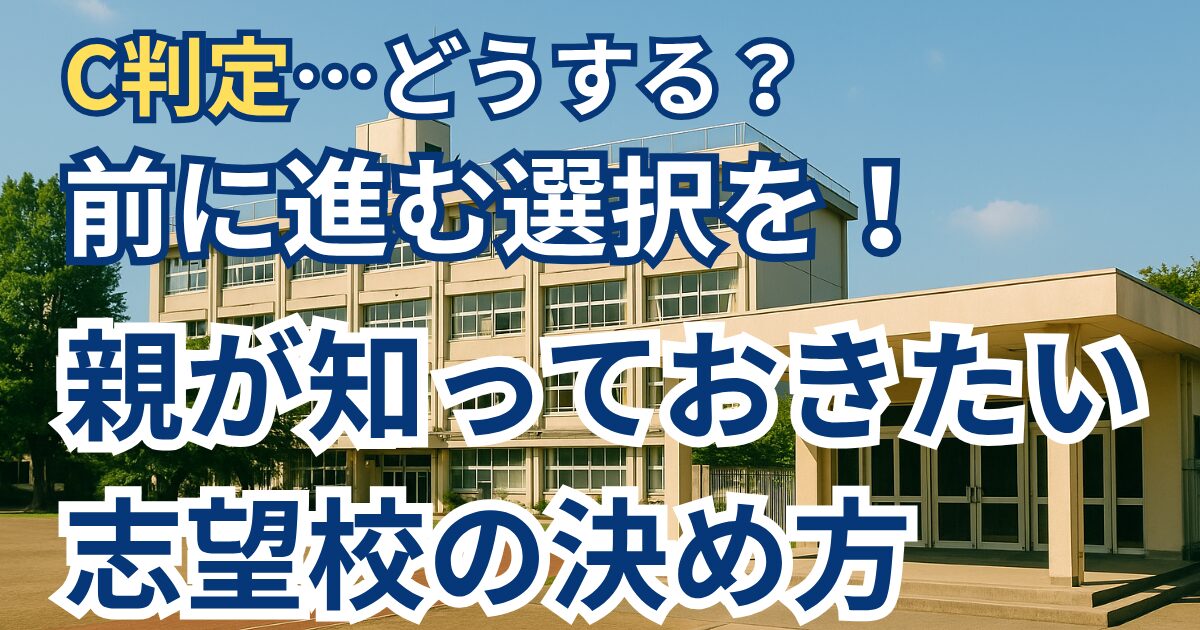
-
【都立高校志望の決め方】VもぎC判定でも迷わない!親が知っておきたい“現実ライン”と併願バランス
続きを見る
Vもぎ後の復習が成績アップのカギ!

模試のあと、復習が疎かになりがちですが、ここをしっかりやるかで伸びが全然違います!
作文・英作文の添削結果をどう活かす?
国語の200字作文や英語の英作文は、自分での採点が難しいため、模試で添削してもらえるのは貴重な機会です。
返却された答案では、減点ポイントや採点の観点をしっかり確認しましょう。
正答率で優先順位をつけて効率よく復習
模試の結果には、各問題の正答率が記載されています。
- 正答率50~80%以上の問題は「絶対に落とせない問題」
- 正答率5~10%未満の問題は「落としてもOK、気にしない」
正答率の低い難問を落としても気にせず、逆に正答率の高い問題は必ず取れるようにしておくのが鉄則。
高校入試では、1問のミスが合否を左右することもあるため、「落としてはいけない問題」を確実に取る意識が大切です。
模試は本番と違い、やり直しができる貴重な場。
結果を受け止め、戦略を立て直すために、しっかり活用していきましょう!
▷模試で見えた苦手を克服するには、日々の家庭学習がカギ
-

-
【中学生の家庭学習】レベル別おすすめ問題集と効果的な使い方ガイド
続きを見る
よくある質問|Vもぎに関するQ&A
初めてのVもぎは、わからないことだらけ。
「親はついて行ったほうがいい?」「昼食はどうする?」「何回受ければいい?」など、よくある質問をまとめました。
Q1:Vもぎは親が一緒に行ったほうがいいですか?
A:基本的には子どもだけで受験します。
送迎はOKですが、会場周辺への車の乗り入れは禁止されているので、離れた場所に停めて徒歩で送るのがおすすめです。
Q2:昼食は必要ですか?
A:Vもぎは昼休みがなく、午前中〜昼過ぎまで一気に行われます。
食事ができないため、すぐ口に入れられるブドウ糖などを持たせると安心です。
Q3:何回くらい受けるのが目安ですか?
A:中3の9月〜1月で月1回ペース(計5回程度)が理想です。
特に12月・1月の模試は本番レベルに近く、最終確認の機会として重要です。
Q4:結果はいつ出ますか?どこで確認できますか?
A:結果は受験から約1週間後、進学研究会のマイページで確認できます。
Q5:判定が悪かったときはどうすればいいですか?
A:1回の結果で落ち込まず、成績の推移を重視しましょう。
正答率を見て「落とせない問題」を重点的に復習するのがおすすめです。
Q6:V模擬・ブイ模擬との違いはありますか?
A:どれも同じ模試を指します。
現在は主催元(進学研究会)が「Vもぎ」表記を使用しており、この記事もそれに統一しています。
まとめ|模試は“練習試合”!判定に一喜一憂しすぎず活用を
Vもぎを受けるときのポイントは以下の通りです。
- 受ける目的:自分の実力を知り、入試本番のシミュレーションをするため
- 受験回数:9月〜1月に月1回+直前の仕上げで計5回程度が目安
- 会場選び:「志望校でのテストを体験」か「アクセスの便利さ」のどちらかで判断
- 親の付き添い:基本は不要だが、送迎や待機などサポートは可能
- 当日の流れ:朝早く集合し昼食は不要。軽食やブドウ糖など小物を持たせると安心
- 結果の見方:判定に一喜一憂せず、成績の推移や正答率を重視する
- 復習の重要性:作文や英作文の添削、正答率の高い問題の取りこぼしチェックがカギ
Vもぎは「練習試合」。
判定そのものよりも、経験を積んで戦略を立て直すための機会として活用するのが一番大切です。