
夏期講習って行かせるべき?
けっこう高いけど、どれぐらい取ればいいのかな…
夏が近づくと、塾から届く「夏期講習のご案内」。
塾に通っているご家庭なら、6月にはもう受講科目や日程の相談が始まりますよね。
でもこの時期、何となく不安だから…と“言われたまま申し込んでしまう”家庭も意外と多いのです。
また、塾に通っていないご家庭でも「夏期講習だけは通わせたほうがいいのかな…?」と迷うことがあるかもしれません。
今回は、塾講師として多くの生徒を見てきた経験、そして親として子どもの夏期講習に悩んだ経験をもとに、
「講習は本当に必要なのか?」「どんな子には合うのか?」をリアルに解説します!
家庭でできる夏の学習法も紹介していくので、講習を取るか悩んでいる方はぜひ参考にしてくださいね。

夏期講習の費用はどれぐらい?塾の営業のしくみ
夏期講習というと、なんとなく「やらなきゃいけないもの」「受けておくのが安心」と思いがちですが、実は塾側の事情が大きく関係しています。
ここでは、夏期講習の収益の仕組みや、おおよその費用について紹介します。
夏期講習は大きな利益となっている
夏期講習は、塾にとって大きな収益源です。
通常授業は料金を抑え、講習でその分を“補う”という料金体系を取っている塾も少なくありません。
講習の日程や受講パックが、必ずしも一人ひとりに最適化されたものとは限らず、 「どれだけ取ってもらうか」を重視した営業スタイルになっているケースも見られます。
実際、夏期・冬期の講習で売上の多くを確保している塾もあり、 この時期に生徒数や営業成果を重視する方針の塾は一定数存在します。
「これ全部やった方が安心ですよ」と提案される内容が、本当にお子さんに必要なものかは、 一度立ち止まって考えてみる必要があります。
費用はどれぐらい?
一般的な大手の集団塾では、だいたい5教科がパック受講になっています(3教科を選べる場合もあります)。
授業は、たとえば「5日間×4回」のように分かれ、1日で3〜5教科を受講するのを5日間繰り返し、数日の休みを挟んでからまた5日間……というサイクルを4〜5回繰り返す形式が一般的です。
基本的には、どこかを休んでもその分の授業料が返金されることはなく、自分の都合で部分的に削ることは難しい場合がほとんど。
料金は教室や学年によって異なりますが、5教科パック+夏期教材費+夏期のテスト・模試費で5~10万円、受験学年になると10万円以上になることが多いです。
また、個別指導塾では、最近主流なのは「3〜5日間で1講座」となっている形式です。
1講座(1教科)の60〜90分授業を、3回または5回受講するもので、その期間の日程は基本的に固定されています。
時間帯は選べますが、「2日間だけにしたい」「日程をばらばらに組みたい」といった柔軟な対応は難しいケースがほとんどです。
1講座(3〜5回)で15,000〜20,000円ほどかかり、例えば英語・数学をそれぞれ9回受講すると、各教科で3講座ぶんとなり、 18,000円 × 3講座 × 2教科 = 約10万円強になります。
さらに理社も加えたり、回数を増やしたりすると、20万円~それ以上かかることも珍しくありません。
| 項目 | 集団塾 | 個別指導塾 |
|---|---|---|
| 授業形態 | パック授業(主に5教科) | 1講座=60〜90分×3〜5回 |
| 教科数 | 5教科(3教科選択可能な場合あり) | 教科ごとに講座単位で選択 |
| スケジュール例 | 5日間×4回などを繰り返し | 1教科につき3〜5回の授業、日程固定 |
| 日程の柔軟性 | 日程・教科の変更不可、欠席分の返金なし | 時間帯選択可、日数調整は不可 |
| 費用目安 (一般学年) | 5万〜10万円 (教材費・模試代含む) | 英数3講座ずつで10万円前後 |
| 費用目安 (受験学年) | 10万円以上が一般的 | 20万円~それ以上 |
夏期講習が“効果的な子”と“向かない子”

夏期講習が本当に効果を発揮する子と、逆に疲弊して終わってしまう子がいます。
ここでは、その違いについて詳しく見ていきましょう。
短期集中がプラスに働くのは“ある程度自走できる子”
夏休みという特別な期間に、いつもと違う形で集中的に勉強することが、良い刺激になる子もいます。
たとえば、
- 普段から勉強の習慣がある
- 自分の苦手や目標をある程度把握している
- 授業をしっかり聞いて、宿題にもちゃんと取り組める
このタイプの子にとっては、夏期講習はペースを維持しながら新しい内容にも取り組めるよい機会になります。
偏差値50以下・勉強習慣がない子には“詰め込み”は逆効果に
逆に、普段から勉強習慣があまりない子にとっては、
毎日長時間塾に通い、大量の内容を詰め込む夏期講習はかなりきついものになります。
実際、詰め込んだ内容は定着せず、集中力も続かず、
「ただ座っていた」「よくわからないまま終わった」というケースも珍しくありません。
人間はそんな短期間で知識を爆発的に吸収するようにはできていません。
特に夏は暑さで集中力も落ちやすく、体力的にも無理が出やすい時期です。
「毎日塾に行ってるから安心」と思っていても、実は中身はスカスカ…なんてことも。
夏期講習だけ違う塾に通うのはアリ?注意点と考え方

「普段は塾に通っていないけれど、夏だけは塾に行って必要なところだけ学びたい」 そんなふうに考えるご家庭もあると思います。
その背景には、
- 普段は習い事やクラブチームで忙しい
- 塾の費用をなるべく抑えたい
といった事情があることでしょう。
たしかに、一見すると「夏だけ通って弱点を補強できれば効率的」と思えます。
ですが、大前提として、塾側は“継続して通ってくれる生徒”を求めているということを知っておいてください。
たとえば、夏期講習で体験授業を受けられる大手塾も多くありますが、それはあくまで「2学期以降も継続して入塾してくれる生徒の募集」の一環。
塾のカリキュラムは基本的に年間設計されているため、夏期講習だけで学習内容を完結させるのは難しいのが現実です。
個別指導塾の場合は特に、最初はその子の学力の土台や弱点を見極めて補強するところからスタートします。
「やっと苦手が改善してきた…」というところで辞めてしまうと、本来伸びるはずだった部分が中途半端で終わってしまうリスクも。
では、夏だけ塾に通うのは完全にNGなのか?というと、そうでもありません。
以下のようなケースなら、効果的に活用できる可能性があります。
- 偏差値60以上、通知表も4〜5が中心で、自分の苦手だけを明確に補強したい目的がある子
- 講習だけで完結するカリキュラムを提示してくれる塾や、短期通塾を認めている塾
この2つに当てはまる場合は、夏だけの通塾でも十分成果が期待できます。
逆に、
- 成績にばらつきがある
- 勉強習慣が安定していない
- そもそも何をやるべきか曖昧な状態
このような場合、夏だけの通塾はおすすめできません。
なお、「夏をきっかけに塾を探してみたい」「秋以降に通塾するか迷っているから、お試しで講習を受けてみたい」という場合は大いにアリ。
その講習で「この塾は合わないな」と感じたら辞めてもいいし、 「ここなら続けられそう」と思えば2学期以降につなげてもOKです。
最初から「夏だけで完結させる」つもりで塾を利用することは、塾側にとっても、子どもにとってもあまり良い選択とは言えません。
「そもそも塾に通うべきか?」で迷っている方はこちらも参考にしてください
講習が必要な子はどんな子?見極めるポイント

夏期講習が「うちの子に本当に合っているのか?」を見極めるためには、実際によくあるミスマッチ例を知っておくことも大切です。
ここでは、私自身の経験を交えてご紹介し、実際にどんな子に講習が合っているのかを解説します。
体験談:理科が得意な息子に、不要な講座が組まれてしまった
わが家の例では、息子は理科が得意だったのに、
講習のパックに含まれていたために理科も受講しなければならず、
逆に本当に必要だった英語と数学の時間に疲れて集中できないという事態に。
しかも、講習の内容には「十分理解できているる単元」もあり、
逆に「ここをやってほしい!」という重要単元がサラッと1回で終わってしまったことも。
特に集団塾の場合、カリキュラムが固定されていて、
子ども一人ひとりに最適化されているわけではありません。
講習の内容をよく見ると、「せっかくお金を払ったのに、ムダが多い…」ということも少なくないはずです。
「勉強する姿勢だけ見せて実はボーッとしている」問題
また、親としては「家では勉強しないから、せめて塾へ」と思うこともあります。
それ自体はとても自然な感情ですし、責められるものではありません。
でも、塾に行ったからといって、実際に“頭を使っているか”はまた別問題。
「とりあえず座ってるけど、頭の中は空っぽ」という子も、正直かなり多いのが現実です。
しかも、夏期講習の料金は決して安くありません。
「行ってはいるけど、身になっていない」となれば、本当にもったいないことです。
さらに厄介なのは、親も子ども自身も、「塾に行った」ことが「勉強をした」とすり替わってしまうケース。
実際には学習が進んでいないのに、「やった気分」になって安心してしまっていることもあります。
親ができる“見極めポイント”
「じゃあ結局、どうやって夏期講習を選べばいいの?」という疑問に答えるために、 親として確認しておきたいポイントをまとめました。
- 今、子どもは何に困っている?
- どの教科をどこまで復習・予習したい?
- 家での学習状況や、夏休みの過ごし方は?
「全部取らなきゃ不安」「塾の先生に言われたから…」ではなく、 まずは「その講習、うちの子に本当に必要?」と考える視点が大事です。
先生の説明が「営業っぽいな…」と感じたら、一度冷静になっても大丈夫。
逆に、「ここは本当に取っておいてほしい」と、 個別に強くすすめてくれる先生なら、信頼して話を聞いてもいいと思います。
「全部受ける or 全部断る」ではなく、 我が子に必要なものだけを選ぶ目を、親が持つことが大切です。
夏休みの家庭学習でできること
夏期講習を取らないからといって、勉強ができないわけではありません。
むしろ、家庭でじっくり進めることの方が合っている子もたくさんいます。
ここでは、「家庭学習でどんなことができるか」と、「親が家にいない時間の学習の工夫」について、2つに分けてご紹介します。
家庭で進める学習の工夫と教材選び
夏期講習を取らないからといって、勉強ができないわけではありません。
むしろ家庭でじっくり進めることの方が、合っている子もたくさんいます。
講習を受けない=勉強しない、ではありません!
夏休みこそ、家庭でコツコツ取り組む絶好のチャンスです。
- 前学年のまとめ教材に取り組む(市販の総まとめ系ドリルなど)
- 1学期の復習:学校ワークのやり直し、テストの解き直し
- 2学期の予習:わかりやすい問題集で先取り(Amazonなどで探せます)
また、学校や塾の教材をコピーして繰り返し使うのも◎。
家庭用プリンターがあると、復習プリントや小テストも作りやすくなります。
「プリント学習」×「小さなToDo」の積み重ねが、夏の学習にはとても効果的です。
カラー印刷にこだわらないなら、レーザープリンター&コピー機が圧倒的に便利!
最近のレーザープリンターはコンパクトで低価格です。
“勉強環境のインフラ”として、1台あると大きな助けになりますよ。

我が家でコピーや印刷に使っているのはこの機種です
教材についてはこちらの記事に詳しく書いてあります
親がいない日中、子どもがさぼらず勉強するには?
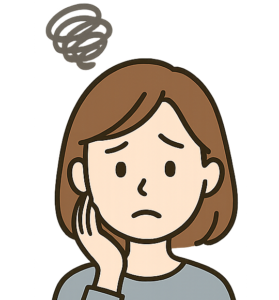
私は働いてるから日中家にいないし、子どもが1人でさぼらずにやっているかどうか心配…
その心配はよくわかります!
家にいればゲームやスマホもやり放題。
塾に行けば少なからず他人の目がありますから、家にいるよりはやるかもしれません。
ただし、
- 「授業があるから必ずその時間は学習している」
- 「自習に行っているからずっと集中して勉強している」
…とは言い切れないのが実情です。
家にいたとしても、ずっと集中している必要はありません。
たとえば「30分勉強して30分休む」でもOK。
「このテキストを◯ページ終わらせたら自由時間にしていい」など、本人がやりやすい“ノルマ型”の進め方がおすすめです。
仕事の休憩中にLINEで「どう?問題集できてる?」「疲れたらおやつ食べなよ」と聞いたり、 帰宅してから「勉強進んだ?」と聞くだけでもある程度の“見守り”になります。
ただし、あまり勉強が進んでいない時に「なんでちゃんとやらないの!」と責めることはおすすめできません。
正直に「わからない問題が多くてやる気出ない」などと言ってきたら、 「じゃあ抜かして別なところやれば?」「後でわからないところは先生に聞けばいいよ」と、 受け止めつつアドバイスするのが理想です。
少なくとも、「塾でしか勉強できない子」になってしまうよりは、 家で一人でも机に向かえるようにしておくことは、決して損にはなりません。
高校進学後や将来を考えても、“家庭での学習習慣”を育てることはとても大切です。
中学生の自宅学習スケジュール例はこちらの記事で紹介しています
【まとめ】講習を受ける前に考えてほしいこと
講習を取ることは、決して悪ではありません。
でも、“目的がはっきりしていること”“本人に合っていること”が大前提です。
信頼できる先生からの提案で、「この単元だけは受けたほうがいい」と
明確な理由があるなら、それは受ける価値があると思います。
一方で、何も考えず「全部申し込む」も、「全部断る」も、危うい選択肢です。
- 今のわが子にとって、必要なのは何か?
- その講習、本当に効果的に活用できそうか?
そして、塾にすべてを任せるのではなく、
「この夏を使って、家庭でも勉強習慣をつけていく」ことも、親としての大切な視点です。
必要なことを、必要な形で取り入れていく。
そんな柔軟な選択ができれば、夏期講習も家庭学習も、きっと意味のあるものになります。




