冬休みが近づくと、塾から冬期講習の案内が届きますよね。
でも実際のところ、冬休みは短くて、帰省や予定もぎっしり。
「うちは受けたほうがいいのかな?」
「行かなくても大丈夫?」
と迷うご家庭も多いのではないでしょうか。
この記事では、塾講師として多くの生徒を見てきた筆者が、冬期講習の本当の位置づけと、やらない選択もアリな理由を本音でお伝えします。
中1・中2・中3それぞれに合った過ごし方や、家庭でできる冬休み勉強法も紹介します。
▷夏期講習について知りたい方は、こちらの記事もどうぞ。
-

-
夏期講習、ほんとに必要?
塾講師が教える
取るべき子・取らなくていい子の違い続きを見る
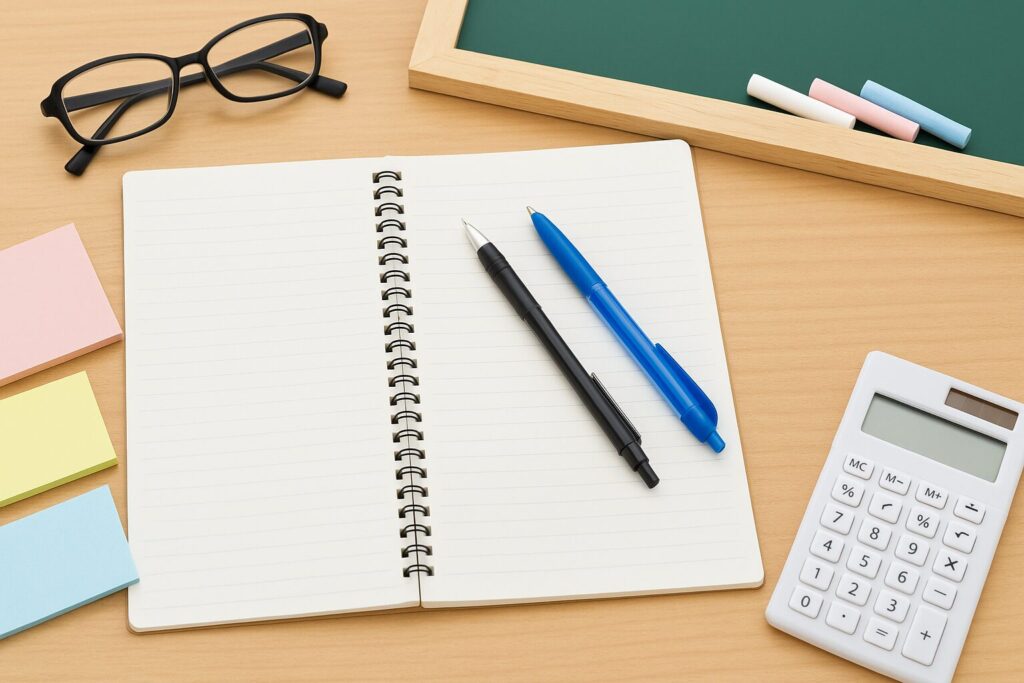
この記事でわかること
- 冬期講習の本当の目的と、塾がすすめる理由
- 学年別に見る「受けたほうがいい子」「受けなくても大丈夫な子」
- 冬期講習を断りたいときの伝え方と家庭での代替学習
- 実際に筆者家庭で行った“受験当日シミュレーション”の効果
冬期講習の“現実”|短期間・詰め込み・営業色も強め
冬休みはあっという間に終わります。
実際に塾の冬期講習を見ていると、実働日数は一週間あるかないか、長くても10日ほどしかありません。
内容も「2学期の復習・3学期の予習」か「入試演習」が中心で、「この講習で一気に成績を上げよう!」というよりは、勉強モードを切らさないための期間に近いです。
また、冬期は塾にとっても営業の山場。
合宿・正月特訓・入試直前ゼミなど、いろいろな講座が組まれます。
もちろんどれも意味はありますが、現場の実感としては「勢いづけ」「気合い入れ」という面が強いのも事実です。
中1・中2にとっての冬期講習|“やらない選択”もアリ

冬休みに限らず、長期の休みは生活リズムが崩れやすい時期。
夜更かししたり、朝起きるのが遅くなったり。
だからこそ、この時期に大事なのは“詰め込むこと”より、“整えること” です。
塾に数日通うよりも、家で1日30分でも机に向かう習慣を保つ方が、次につながります。
たとえば
- 学校のワークを見直す
- 英単語を1日10個だけ復習
- 冬休み明けテストの範囲をチェック
こんな小さな積み重ねで十分。
「冬は無理せず整える」「春からが勝負」くらいの気持ちでOKです。
▷中学生の家庭学習を整えたい方はこちらもおすすめ。
-

-
【保存版】中学生の自宅学習スケジュール
生活習慣から整える勉強時間の作り方続きを見る
中3の冬期講習|“メンタル安定”と“安心感”のために
受験生にとって冬期は、まさにラストスパート。
でも、正直に言えばこの時期に大きく学力が伸びる子はそれほど多くありません。
むしろ大事なのは、焦りをコントロールして、日々のやることを積み重ねること。
塾に行くことで「みんなで頑張ってる」「自分も遅れちゃいけない」という雰囲気に助けられる子もいます。
そんな子にとっては、冬期講習でみんなと一緒に勉強するのが良いかもしれません。
一方で、長時間の授業や人の多い環境がストレスになる子もいます。
そんな場合は、家でじっくり勉強するのも立派な選択。
この時期の受験勉強は、量よりも「心を乱さない」ことのほうが大事とも言えます。
わが家の冬休みの過ごし方(体験談)

わが家でも、息子と娘でまったく違いました。
息子は中3のとき塾の冬期講習に参加しましたが、コロナの影響でオンラインに切り替わってしまい、家でだらだら受けるだけに…。

オンライン授業中に勉強部屋をちょっと覗いたら、
キャスター付きの椅子で部屋の真ん中をクルクル回っていました…
案の定、あまり効果を感じませんでした。
一方、娘は塾に行かず家庭学習中心。
模試の復習をしたり、苦手な英語をコツコツやったり。
のんびりペースでしたが、むしろ落ち着いて過ごせてよかったです。
そしておすすめなのが、「受験当日のシミュレーション」を冬休みに一度やってみること。
当日のスケジュール通りに起床し、ごはんを食べて、試験時間に合わせて過去問を解く。
お昼休みの時間にお弁当も実際に食べてみる。
この練習がすごく有効で、本番の流れを体でつかめました。
▷受験当日は緊張で食が進みにくいので、温かいお弁当は本当に助けになります。
受験生に向いている保温弁当箱の選び方と、男子・女子別のおすすめはこちらの記事で。
-

-
温かいごはんがお昼まで続く!
サーモス保温弁当箱の選び方
受験生にも役立つ2つの違い続きを見る
冬期講習を断るときの伝え方と考え方|塾講師が語る「無理しない選択」
塾で働いているとわかりますが、
冬期講習をすすめるのは、もちろん営業の一環でもあります。
そのため、保護者としては「断りづらい…」と感じることもありますよね。
でも、そこは気にせず、次のようにはっきり伝えて大丈夫です。
- 「うちは家庭学習でやるので、今回は見送ります」
- 「部活と帰省があって、スケジュール的に難しいです」
ただし、普段あまり勉強をしていなかったり、成績が低めのお子さんの場合、塾から「講習だけでも受けてください」と言われることもあります。
これは、決して売上のためだけではなく、「勉強の習慣を止めないでほしい」という教育的な理由でもあります。
せっかく身につけた勉強リズムが、数週間で途切れてしまうのは本当にもったいないこと。
家庭でまったく勉強できないタイプの子なら、短時間でも塾に通って刺激を受けるのは意味があります。
とはいえ、長時間のスケジュールで集中力が切れるようなら逆効果。
ただ座って時間を過ごすだけになってしまっては、せっかくの講習がもったいないですよね。
大切なのは、塾に行く・行かないよりも「勉強習慣を止めないこと」。
塾に通わなくても、自分のペースで勉強を続けられるなら、それで十分です。
▷塾に行っても成績が伸びない…そんなときのヒントはこちら。
-

-
成績が上がらない中学生の7つの原因
塾に行っても伸びない理由と親の見直し方続きを見る
まとめ|冬期講習は“整える季節”ととらえよう

冬期講習は、「成績を上げる魔法」ではありません。
でも、「生活リズムを立て直す」「不安を落ち着ける」には大いに役立ちます。
行く・行かないよりも、「どう過ごすか」を家族で考えることがいちばん大事。
塾に行かなくても、家で机に向かう時間を少しずつつくれたら、それが何よりの冬の収穫になります。
やらない選択にも、自信を持って。
「うちのペースで冬を過ごす」ことが、次の春につながります。

冬期講習の時期、塾では正直“断りづらい空気”もあります。
でも、家庭の状況も子どもの性格も十人十色。
「行かないこと=怠け」ではなく、
“わが家なりの選択”として受け止めていいと思っています。
この冬は、少し肩の力を抜いて、お子さんと“我が家らしい冬の過ごし方”を考えてみてくださいね。
