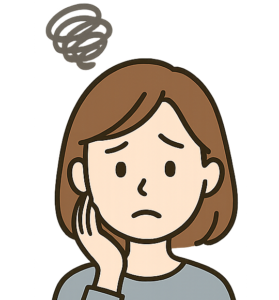
うちの子、成績が悪くてやる気もない…
ちゃんと高校に行けるのかな
「成績が悪いけど、このままで将来大丈夫…?」
中学生の子を持つ親なら、一度は不安になるテーマですよね。
結論から言うと、成績が悪いからといって将来がダメになるわけではありません。
私自身、塾講師として10年以上中学生を見てきた経験と、2人の子どもを都立高校に送り出した母としての実体験から言えるのは――成績の良し悪しだけで将来は決まらない、ということです。
ただし、社会で活躍するためには「自己管理力」「計画性」「人との関わり方」といった“成績以外の力”が欠かせません。
この記事では、
- 成績と将来の関係
- 社会で活躍する子に共通する力
- 親ができる“導き方”
を整理してお伝えします。


「成績が悪いと将来困る」は本当?
成績が悪いと将来が不安…それは、多くの保護者が抱く自然な感情です。
実際、統計的に見れば「大卒と高卒で生涯年収に差がある」「良い企業に入るには学歴が影響する」といった傾向はあります。
また、大学卒業者の方が初任給が高くなるケースが多いことも事実です。
ただ、今の時代は“大学全入時代”とも言われていて、選ばなければどこかしらの大学には入学できるという現実もあります。
つまり、進学という面で見れば、ある程度の学力があれば道は開ける。
そして、その“ある程度”は、今の成績が少し悪いからといって絶望するほどのものではありません。
それでも、心配になってしまうのは「わが子のことだから」。
「このまま成績が伸びなかったら…」
「ちゃんと働ける大人になれるのかな」
そんなふうに思ってしまうのは、ごく当たり前のことです。
でも大切なのは、“今の成績”をゴールのように捉えないこと。
大人になったとき、社会の中で自分らしく生きていける力が育っているかどうか─。
そこに目を向けてみると、少し違う景色が見えてきます。
親がもつ“理想の子ども像”と、現実のズレ

「大学には行ってほしい」
「せめてこの高校には入ってほしい」
こうした願いは、多くの場合、親自身の経験や価値観からくるものです。
自分が大卒なら「大学は出てほしい」、自分が高卒なら「自分よりは上の学歴を」と思うこともあるでしょう。
もちろん、子どもを思う気持ちがあるからこそ、そう願うのは自然なことです。
けれど、その“理想の子ども像”が、今目の前にいる現実の子どもと大きくズレているとき、親子関係は苦しくなりがちです。
オール5の子でも「もっと上を」と求められればプレッシャーに。
オール2の子でも「今のままでいいよ」と言ってもらえれば、安心して前を向けることもあります。
子どもを“理想に合わせよう”とするのではなく、
「この子は今、どんな力を持っていて、何を大事にしているのか」を見つめ直すこと。
その視点が持てると、親子で前向きな関係を築く第一歩になるかもしれません。
▷「成績が悪いのは母親のせい?」と悩んでしまう方に向けて、私自身の経験をまとめた記事もあります。
-

-
子どもの成績が悪いのは母親のせい?元塾講師ママが伝えたい本当の理由
続きを見る
社会で活躍できる子に共通する力とは?
塾講師としてたくさんの子どもたちと接してきた中で、成績の良し悪しに関係なく「この子は将来きっと大丈夫だな」と感じる子たちには、ある共通点がありました。
それは、自分の言葉で気持ちや考えを伝えられることです。
たとえば、宿題を忘れたときに「やってない」と正直に言える。
叱られたときに「次は気をつけます」と返せる。
意見があるときに「私はこう思う」と言葉で伝えられる。
うまく言えなくてもいいんです。言葉が足りなくても、間違っていてもいい。
大切なのは、“伝えようとする力”があること。
そしてもうひとつは、相手の言葉を受け止める力。
注意されたときに耳をふさがずに聞けるか、
話している相手の表情や空気を感じながら受け答えができるか。
こうした“コミュニケーション力”は、どんな職場でも、どんな立場でも必要になります。
私が若いころに塾で教えていた生徒たちは、今や社会人として家庭をもち、親となっている子もいます。
中学生・高校生時代の成績はさまざまでしたが、当時から自分の言葉で話し、相手の言葉を受け止められる子は、今もそれぞれの場所で、生き生きと自分の人生を歩んでいる印象です。
偏差値が高い・低いに関係なく、社会の中で人と関わり、自分の居場所を作っていくために必要な力。
これを中学生のうちから少しずつ育てていくことは、勉強以上に大きな意味を持つかもしれません。
身につけておきたい“将来につながる習慣”

社会に出たとき、周囲と協力しながら生活を回していくためには、「スケジューリング」や「タスク管理」のような力がとても役立ちます。
たとえば、
- 学校の提出物を忘れないようにする工夫
- 部活や習い事との両立に合わせた勉強の計画
- テスト前のやることリストの整理
こうした力は、特別な才能ではなく「習慣」で身につけていくもの。
だからこそ、中学生のうちに、親が一緒に考えてあげることがとても大切です。
また、生活リズムが乱れがちな子ほど、将来も自己管理に苦労しがち。
夜更かし、朝食抜き、忘れ物…そうした日常の“つまずき”を、親が優しくサポートしてあげることで、子どもの中に「整える力」が育っていきます。
実際に、社会に出てから苦労せずやっていける子は、スケジュール感覚や“やるべきことをやる習慣”が、ある程度身についていました。
それは、親がガミガミ言ってつけさせたというより、「いっしょに考えて導いてきた」結果として、自然に身についたもの。
勉強の内容そのものより、こうした“日常の基礎力”こそが、将来の土台になるのだと感じています。
親が果たす「導く役目」とは

子どもの成績が思うように伸びないとき、親としてできることは限られているかもしれません。
でも、“変える”ことはできなくても、“導く”ことならできます。
たとえば、目標の高校や、やりたいことを一緒に探してあげること。
少しずつでも、その目標に向かって努力できるように声をかけること。
そして、勉強の成績だけでなく、社会で生きていくために必要な力──
スケジューリングや自己管理、コミュニケーションなど、
日々の生活の中で少しずつ身につけられる力を育てていくこと。
そのサポートをするのが、親の大切な役割です。
子どもは親の思いどおりには育ちません。
けれど、「自分らしく生きられる力をつける」
そこをゴールにしてサポートしていけば、親としてできることはきっと見えてきます。
成績の良し悪しにとらわれすぎず、その子の強みやペースを信じて寄り添う。
その積み重ねが、子どもにとっての“生きる力”になっていくはずです。
▷成績が悪い子が将来どうなるのか?私自身の経験をもとに「本当に大事な力」と親の関わり方をまとめた記事もあります。
-

-
中学生の成績が悪い…将来どうなる?塾講師が見た“本当に大事な力”と親の関わり方
続きを見る

まとめ|「成績が悪い=将来ダメ」ではない
この記事のポイントをまとめました。
- 成績や学歴は進学や就職に影響することもあるが、将来すべてを決めるわけではない
- 社会で活躍できる子は「自分の言葉で伝える力」「相手の言葉を受け止める力」を持っている
- 日常の習慣(提出物管理・生活リズム・タスク整理)が、将来の土台になる
- 親は“変える”のではなく、“導き・寄り添う”ことで子どもの強みを伸ばせる
中学生の今、成績だけにとらわれず、子どもの「生きる力」を信じて寄り添ってあげましょう。
それが、将来につながる一番のサポートになります。
▷関連して読んでおきたい記事
-

-
成績が悪い中学生に、親が“やるべきこと”と“やらなくていいこと”
続きを見る
-

-
中学生の成績が悪いと都立高校はムリ? チャレンジスクール・専科・通信制まで徹底解説
続きを見る
