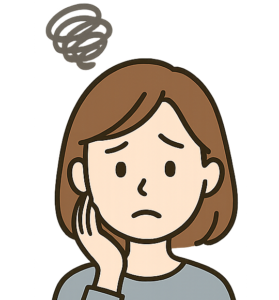
えっ…また提出物出し忘れたの!?
「せっかくやったのに提出していなかった」
「机の上に置きっぱなしで出し忘れた」
中学生の提出物トラブルって、本当によくありますよね。
私もママ友や塾の生徒の保護者から、何度も愚痴を聞いてきました。
もちろん、うちの子だって例外ではありません…。
しかも提出物は、ただの宿題ではなく 内申点に直結する大事な要素。
「まあ、忘れてもいいか」では済まされない部分があります。
そこで今回は、元塾講師&母としての経験から、提出物を出さない子への親の支え方をまとめました。
提出物と内申点はどう関係している?
提出物は、ただの「宿題」や「練習問題」じゃありません。
実は通知表の評価に強く影響していて、内申点を左右する大きなポイントなんです。
特に「意欲・関心・態度」といった観点の評価では、提出物の有無や丁寧さがしっかり見られています。
どんなにテストで点数を取っても、提出物を出さないだけで評価が下がることもあるんです。
つまり、提出物は「学力アップのため」より「内申点アップのため」に欠かせないもの。
推薦入試や内申基準がある高校を狙うなら、提出物を軽視するのはとても危険なんです。
提出物を出さない中学生が多い理由

「なんで出せないの?」「怠けてるだけ?」と思うかもしれませんが、実はそう単純じゃありません。
提出物が出せない主な理由を3つあげてみます。
やったのに出さない
「机に置いたまま忘れた」
「ランドセルに入れ忘れた」
など、やることはやっても最後の“提出行動”までつながらない子は意外と多いです。
そもそも把握していない
何を出すのか把握できていないパターン。
プリントの配布や提出期限を記録する習慣がない子にありがちです。

うちの息子はこのパターンだ…
整理できない
いわゆる「整理整頓」がニガテなのがこのタイプ。
プリントやワークを管理することができず、提出物自体を紛失したり、出すのが遅れてしまうことも。
つまり、「出さない」のは性格の問題ではなく、まだ仕組みや習慣が育っていないからなんです。
▷提出物だけでなく忘れ物も同じように“仕組みづくり”で改善できます
-

-
中学生の忘れ物にイライラ…
怒らずに減らす!親の工夫5選続きを見る
提出物を出さないと内申にどう影響する?
ここからは少し現実的な話を。
提出物が出せないと、内申点にどんな影響が出るのでしょうか?
提出物は「意欲・関心・態度」の評価に直結するので、提出がないと評価が1段階下がることがあります。
例えばテストの点数が80点で「4」に相当しても、提出物の欠如で「3」になるケースも。
受験生にとって、「あと1足りない」「あと2足りない」は本当に大きい差。
推薦や併願優遇がかかった時、提出物の習慣が未来を左右することもあるんです。
▷提出物だけでなく、内申点全体をどう上げていくかの戦略はこちら
-

-
中学生の内申点を上げるには?
提出物・授業態度・検定を味方にする方法続きを見る
親ができる提出物サポート術

「じゃあ親はどう関わればいいの?」
ここが一番知りたいところですよね。
怒るのではなく、仕組みと習慣を一緒につくっていくのがコツです。
ここでは、親が実際にできるサポート法をまとめました。
私自身がやって効果を感じたものばかりなので、安心して取り入れていただけます。
もちろん、全部を完璧にこなす必要はありません。
できそうなところから少しずつ試してみてくださいね。
リスト化して“見える化”
週に一度、子どもと一緒に「提出物リスト」を作る習慣を。
ホワイトボードや付箋で見える場所に貼ると、子どもも意識しやすくなります。
出すまでの導線を一緒に作る
「やったらカバンに入れる」までをセットで習慣化。
最初は一緒に確認し、慣れたら子ども自身ができるように見守りましょう。
「やった?」より「出した?」の声かけ
親はつい「宿題やった?」と聞きがちですが、大事なのは「出した?」。
提出の瞬間まで意識させる声かけが、行動定着に効果的です。
YouTubeやAIで“調べ方”を手助けする
「わからないから手が止まる」→これが提出物が出せない大きな理由のひとつ。
そんなときは、親がYouTubeやAIでサッと調べて導入部分を一緒に見つけてあげてもOKです。
全部を手伝う必要はなく、ヒントを与えるくらいで十分。
答えを写してでも“形”を整える
提出物は「正解の多さ」より「出しているかどうか」が評価される部分。
考え込んで止まるよりは、答えを赤ペンで丸写しでもいいから形にして提出することが大事。
理解はあとからでも追いつけます。
コピーして「提出用」と「勉強用」を分ける
ワーク類は、まず提出用として書き込み、その前にコピーをとっておけば「テスト前にもう一度解く」ことができます。
提出=形を整える/勉強=理解を深める、と分けて考えるとラクになります。
提出物ボックスやタイマーで“行動の導線”を作る
リビングや玄関に「提出物ボックス」を置く、帰宅後30分以内に“提出物チェックタイム”を作るなど、行動をルール化。
物理的に導線を作ると忘れにくくなります。
具体的な内申点や高校名を伝えて現実を見せる
「うるさいなあ」と思われても、現実を見せるのは効果的。
「◯高校の推薦には5教科内申が17必要なんだよ。あと1足りないと受けられないんだよ」と具体的に伝えると、子どもが“提出物=未来に直結”と理解しやすくなります。
▷こちらの記事では、声かけや仕組みの作り方をさらに具体的に紹介しています
-

-
提出物を出さない中学生に悩む親へ!
怒らずできた3つのサポート法続きを見る
まとめ|提出物は内申点アップの第一歩
提出物を出さないのは「怠け」ではなく、仕組みや習慣がまだ育っていないだけ。
でも、その積み重ねが内申点=受験の合否に大きく響きます。
提出物を出すことは、学力アップとは別の「自己管理力」の練習。
親ができるのは「怒る」ことではなく「仕組みをつくり、行動をサポートする」ことです。
今日からできるのは「今週の提出物ある?」と聞くこと。
その一言が、未来の内申点を守る第一歩になりますよ。
