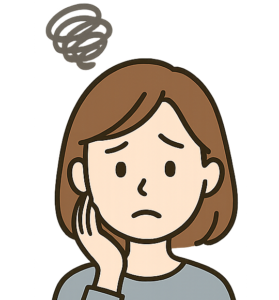
うちの子、中学生なのに全然勉強しない。
部屋にこもったと思ったらスマホ…どうしたらいいの?
「勉強しない」「集中力がない」「そもそも机に向かわない」──中学生の“やる気のなさ”に頭を抱えている親御さん、多いんじゃないでしょうか。
私も塾講師として10年以上中学生を見てきましたが、実際に自分の子どもが中学生になったとき、「えっ、家でこんなにやらないの!?」って驚きました。
でも、その経験から「家庭環境のつくり方」で、勉強への取り組み方がガラッと変わることがわかりました。
この記事では、家庭でできるサポートのひとつとして「リビング学習」に注目し、そのメリット・デメリット、そしてわが家で実際にやって効果を感じた7つの工夫をお伝えします!

中学生が“勉強できない”のは家庭環境も関係ある?
実は子どものやる気のなさ、単なる「サボり」じゃないことが多いんです。
中学生は成長期のど真ん中で、体も心も忙しい時期。
そんなときに、
- 親が何をしてほしいかが伝わってない
- 自室が“娯楽の巣”になってる
- 生活リズムが崩れてる
こんな状態だと、どんなに真面目な子でも「やる気スイッチ」が入りづらい。
「なんで勉強しないの?!」と責めたくなる気持ちはとてもよくわかりますが、それをグッとこらえ、
「勉強できない=家庭にも原因があるかも?」と見直してみることをまずおすすめします。
リビング学習のここがいい!メリット3つ

1. 集中のハードルが下がる
自室だとマンガ・スマホ・ベッド…誘惑がたくさんありますよね。でもリビングなら、遊び道具は少なめで、「何となくやることがないなら、ちょっとやってみるか」と思える空間になります。
特に、勉強が苦手な子は「勉強を始めること」自体が高いハードル。そのハードルを下げてくれるのが、リビングという“気軽な場所”なんです。
2. 親がさりげなく見守れる
何かを教えるわけじゃなくても、同じ空間にいることで子どもは安心します。
「ちゃんと見てくれてる」「ひとりじゃない」と感じることで、やる気の持続にもつながります。
また、親も「どこでつまずいてるのか」「何をしてるか」が自然に見えるので、無理なくサポートできます。
3. 勉強が“日常”に組み込まれる
リビング学習は、特別なことじゃなく“生活の一部”として勉強が入ってくるのがポイント。
部屋にこもる=「勉強しなきゃ」と思って重くなる子でも、 「ごはんのあとにちょこっと」「宿題だけここでやる」くらいの流れで始めると、ストレスが少なく習慣になりやすいです。
こちらの記事も参考にとうぞ
こんな落とし穴も!リビング学習のデメリット2つ
1. ダラダラしがちになる
リビングはリラックスする場所でもあるので、気が抜けすぎると「いつまでも終わらない…」という落とし穴に。
「リビングだからダラダラする」のではなく、「ダラダラしない仕組みを作る」ことが必要です。
2. 家族の生活音・会話が気になる
他の家族の動きや音が気になって、集中できないことも。
特に小さい兄弟がいる場合などは、タイミングを見て「今日は静かになりそうな時間にやろうか」と調整していくのも一つの手です。
やってよかった!わが家のリビング学習7つの工夫
では、実際にリビング学習のためにやってよかった7つの方法を紹介します!
1. 勉強セットはひとまとめに
「やろう!」と思った瞬間にノートがない、えんぴつが削れてない…それだけでやる気が吹き飛ぶこと、ありますよね。
うちは100均のカゴに“リビング学習セット”を用意してました。中身はノート・えんぴつ・赤ペン・消しゴム・ふせん・タイマーなど。
さらに、教科書やノート類はすぐ手に取れる場所に置き、使いかけの問題集やノートを“開いたまま”しまえるように、テーブル下の収納棚も活用しました。
この「やりかけの状態を維持する」って実は心理的にも効果があるんです。
未完了の作業ほど気になって続きたくなる「ツァイガルニク効果」っていう現象もあって、「また続きをやりたくなる」状態が自然とできるんですよ!
2. スマホは届かないところに避難
スマホが手元にあると、気づけば通知を見てゲームやSNSに流れてしまいがち。
うちは「ごはんのときと同じように、勉強中はスマホはリビングの棚に置く」とルールを決めました。
最初はブーブー言ってましたが、数日で慣れました。
「ないほうが集中できる」ことを体感すると、自分から置くようになりますよ!
3. 家族の音は“先にルール化”
勉強中に気が散らないよう、家族みんなに“ちょっとした協力ルール”をあらかじめお願いしておくとスムーズです。
例えば、テレビの音は少し小さめに、電話はできるだけ別の部屋で対応、弟妹には「今お兄ちゃん勉強中なんだよ」と一言伝えておくなど、事前に軽く声をかけるだけでも効果大!
「またテレビつけて!」と注意するよりも、最初から「ちょっとだけ静かにしてもらえると助かる」とお願いするほうが、親も子も穏やかに過ごせます。
わが家では、キッチンタイマーを使って「この15分だけ集中タイムにするね」と宣言していました。
そうすると、家族もその時間だけは自然と静かに協力してくれるように。
4. 親は口を出さず、視界に入るだけ
リビングで勉強させていると、つい「あ、そこ間違ってるよ」「もっと集中して!」なんて口を出したくなりますよね。
でも、それが逆効果なことも多いんです。特に思春期の中学生は、親の言葉に敏感。注意されたり否定されたりすると、やる気がガタ落ちすることも…。
だからこそ、親は“そばにいるけど何も言わない”がベスト。 たとえば、横で洗濯物をたたんだり、新聞を読んでたりするだけでも、「見守ってもらってる」という安心感につながります。
そして、もし子どもに質問されたときには、“答えを教える”のではなく“答えの見つけ方”を伝えるようにしていました。
- 教科書を見直してみるように促す
- ノートを確認するように言ってみる
- 学校の先生に聞いてみようとアドバイス
- YouTubeの解説動画を一緒に探す
こうした“学び方のヒント”を伝えるだけでも、自分で進める力につながっていきます!
さらに、丸つけだけ親が手伝うのもおすすめ。
声かけ+ちょっとした手伝いで、モチベーションがぐっと上がることもありますよ!
こちらでも詳しく書いています
5. 椅子はちょっと硬めでサクッと集中
柔らかいソファやクッション性の高い椅子に座ると、体が沈み込んでそのままリラックスモードに…。
うとうとしたり、姿勢が悪くなったりして、集中力が落ちてしまいます。
うちでは、あえて“ちょっと硬め”のダイニングチェアで勉強していました。
「長時間ダラダラやる」より「短時間で集中してサッと終わる」流れに持っていけるので、本人も疲れにくくなります。
勉強専用のイスを買わなくても、クッションを外すなどの小さな工夫でOKです!
6. 短時間集中→休憩→また集中の流れを作る
中学生って、大人が思ってる以上に集中が長く続きません。 なので「ずっとやりなさい」より「15分やって5分休憩」くらいがちょうどいい!
うちはキッチンタイマーやスマホのアラーム機能を使って、
- 15分勉強
- 5分休憩
- また15分勉強
というようなサイクルを作っていました。
最初のうちは「休憩多くない?」と思うかもしれませんが、逆にこのほうがダラダラが減ってトータルの勉強量は増えることも。
本人のリズムに合ってくると、自分からタイマーをセットするようになりますよ♪
もう少し長い25分の集中と5分の休憩を繰り返す「ポモドーロ・テクニック」という方法もおすすめ。
YouTubeにこのテクニックを使った勉強用タイマー動画がたくさんあるので、テレビでそれを流して“勉強タイムのBGM”にするのも一つの手ですよ。
こちらの記事もおすすめです
7. 終わったら「ごはんにする?」のゆるごほうび
「がんばったあとの楽しみ」があると、子どもは前向きになれます。
勉強が終わったあとに「じゃあ今日のデザート食べようか!」「おつかれさま、晩ごはんにしようか」といった、ちょっとした“ごほうび”があると、本人の満足感がぐんと上がります。
ごほうびと言っても、何か買ってあげる必要はありません。
声かけや食事、おやつ、好きなテレビタイム…そんな小さなことでも十分!
「終わったらいいことある」と思えると、嫌な勉強も「とりあえずやろうか」という気持ちになれるんです。
それでもうまくいかないときは?

もちろん、どんなに環境を整えても「今日はムリ…」という日もあります。
子どもだって疲れているし、気分が乗らないときだってある。
そんなときは無理に続けさせずに、
「今日はここまででOKにしようか」「続きは明日やろう」 といった声かけで気持ちを切り替えてあげるのも大事です。
また、リビングが合わない子もいます。 「やっぱり自分の部屋でやりたい」という場合は、そちらの環境も整えてあげましょう。
たとえば、
- 明るさを調節できるライト
- 足元だけ温められるパネルヒーター
- 最低限の文具だけ置ける机まわり など、シンプルで集中しやすい空間づくりを意識すると◎。
わが家では「寝室」と「勉強部屋(書斎)」を分けたことで、切り替えがしやすくなったという経験もあります。
大切なのは「絶対こうしなきゃ!」と親がガチガチに決めるのではなく、子どもに合ったやり方を一緒に見つけていくこと。
リビング学習もうまく使いつつ、ときには「今日はムリしない日」もOKにして、ゆるく長く続けられる工夫をしていきましょう。
こちらの記事も参考にどうぞ
まとめ:リビング学習は“見守りと仕組み”がカギ!
リビング学習は、やみくもに始めるよりも「環境」と「声かけ」のバランスが超大事。
勉強しない=子どもが悪い、ではなく、“家族全体で勉強モードに持っていく”工夫がポイント!
完璧を目指さなくていい。
今日ちょっとだけ机に向かえたら、それでもう大成功ですよ!




