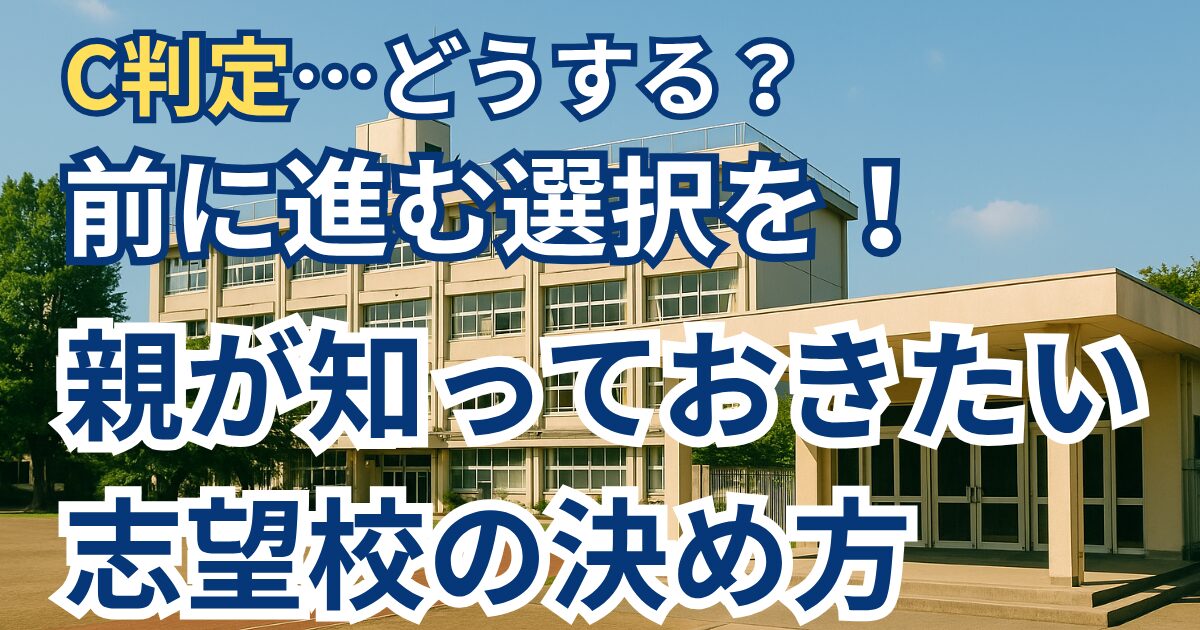志望校がだいたい決まり、模試の結果もいくつか出る中3の2学期。
親も子も、「このままこの高校に挑戦する?それとも下げる?」と迷うことが多いのではないでしょうか。
実際には、最終的な出願校は1月のVもぎ結果で決まる家庭がほとんど。
秋の段階ではC判定あたりをうろうろしている子が多く、第一志望校が安全圏で安心している子はあまりいません。
都立受験は内申+本番の点数で決まるため、「あと少しでB判定に届く」「過去問では手応えあり」など、ギリギリの判断が続きます。
この記事では、そんな時期に親がどうサポートすればいいかを整理します。
▷この記事は【中3の秋〜初冬】を想定して、VもぎC判定の考え方を整理した内容です。
12月後半〜1月のVもぎでC判定が出た場合は、判断の視点が大きく変わります。
そんな受験直前の悩みについては、こちらの記事で詳しくまとめています(結論だけ先に知りたい人向け)。
-

-
【都立】VもぎC判定は厳しい?
出願前に迷わない現実ラインと親のサポート続きを見る

この記事でわかること
- 都立志望を決めるときの“現実ライン”の見極め方
- Vもぎ判定の受け止め方
- 都立×私立併願のバランス調整法
- 下げる判断を責めない親の関わり方
- 安全校を見学しておくべき理由
都立志望を決めたら、現実ラインを知るのが第一歩
志望校を考えるうえでまず大切なのは、「いまの成績でどの位置にいるか」を正しく把握すること。
感覚だけで「もう少し上を狙えるかも」と思っても、都立入試は内申点と当日の点数の合計で決まるため、数字で見ておくことが欠かせません。
ここでは、都立受験の基本的な仕組みと、Vもぎ判定の見方をかんたんに整理しておきましょう。
▷Vもぎの受け方や会場選び、当日の流れについての詳しい記事はこちら
-
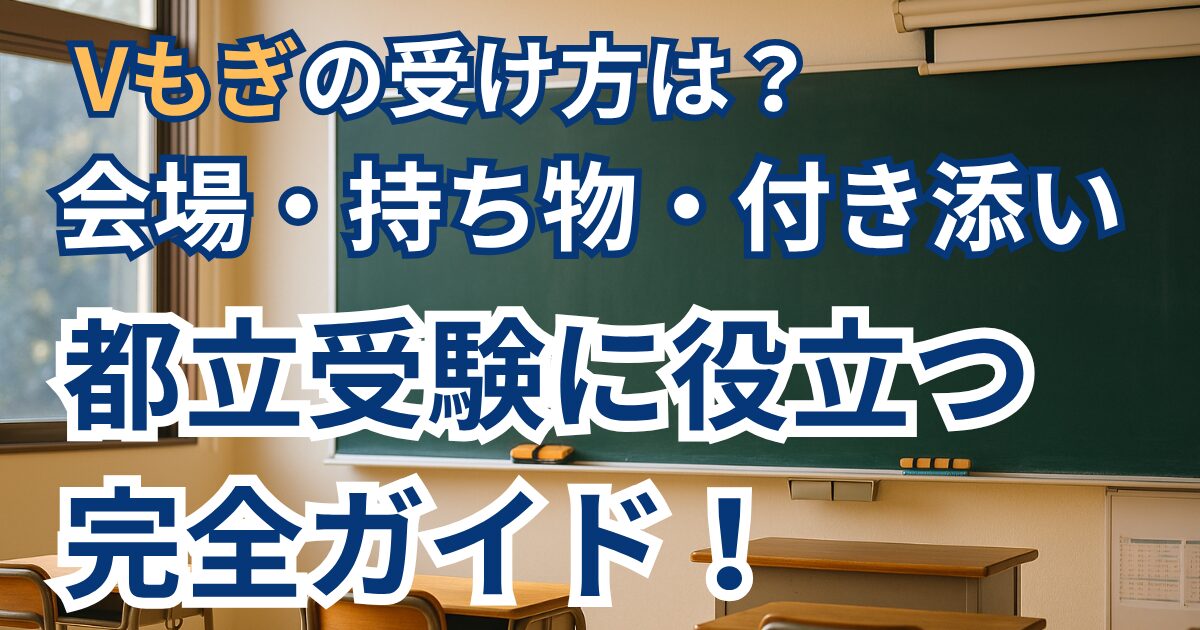
-
【Vもぎ】親は一緒に行く?
受け方・会場選び・何回受けるかまで体験談で解説続きを見る
都立入試の配点を知ろう(1000点+ESAT-J YEAR 3の20点)
都立高校の一般入試は、「内申点+当日の学力検査」=合計1000点満点が基本です。
ここに「ESAT-J YEAR 3(英語スピーキングテスト)」が最大20点加点され、1020点満点になる場合があります。
内訳は次のとおりです。
- 調査書点(内申):300点
- 学力検査(当日試験):700点
- +ESAT-J YEAR 3(最大20点)
学力検査が7割・内申が3割という比率が基本で、学校によっては6:4(学力検査6・内申4)を採用している場合もあります。
なお、「ESAT-J YEAR 3」は令和6年度からの新名称で、中3生を対象にした英語スピーキングテスト。
第一次募集・分割前期募集で活用されますが、英語学力検査を実施しない学校(エンカレッジスクール、チャレンジスクール等)は対象外です。
※配点や反映の有無は学校によって異なるため、最新の募集要項を必ず確認してください。
▽都立入試についての詳しい解説はこちらの記事で。
-
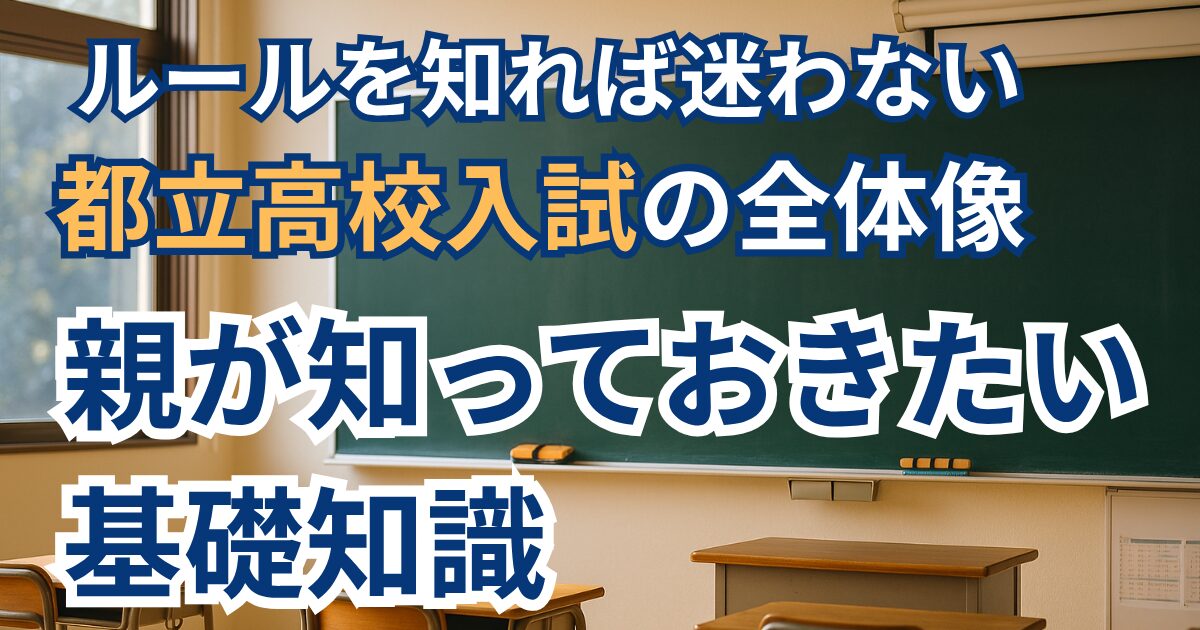
-
【都立高校入試の仕組み】
内申点・学力検査・推薦の流れをやさしく整理
親が知っておきたい基礎知識続きを見る
VもぎC判定は「まだ戦える」けど「安定しない」ゾーン
Vもぎの判定は次のとおりです。
- A判定:合格可能性80%以上
- B判定:60〜79%
- C判定:40〜59%(届くかどうかの境界ライン)
- D判定:20〜39%
- E判定:20%未満
塾で多くの生徒を見てきた経験から言うと、一番悩むのはこの「C判定」。
中3の2学期は、第一志望がC判定という生徒がもっとも多い印象です。
10〜11月の段階でC判定なら、まだ伸びしろは十分。
これから学ぶ範囲も多く、実際に入試で使う「2学期末の内申」もまだ出ていません。
つまり、この時期のC判定はBやAに上がる可能性をしっかり残しています。
ただし、12月のVもぎまでに一度もBやAが出ていない場合は、そろそろ志望校を見直すタイミングかもしれません。
とはいえ、「もう少しでB判定に届く」「過去問では合格点が取れている」など、あと少しで届きそうだからこそ、下げる決断は本当に難しいもの。
だからこそ、焦らず冷静に「今の位置」「あと何点必要か」を数字で見える化しておくと安心です。

うちの子どもたちも、10月の時点で志望校の都立はどちらもC判定でした。
でも11月でB、1月でAに上がり、最終的に第一志望に合格。
C判定は「まだ可能性があるライン」なんだと実感しました。
ただし、これは「秋〜11月ごろのC判定」の話です。
12月後半〜1月のVもぎになると、残り時間や内申がほぼ確定するため、 同じC判定でも意味合いが変わってきます。
そこで、いちどここで「秋のC判定」と「1月のC判定」の違いを整理しておきます。
12月後半〜1月のC判定は「同じC」でも別物。親が見るべきポイント
秋のC判定は“伸びしろがあるかどうか”を見る時期。
一方で、1月のC判定は「残り時間・内申ほぼ確定」の中で、判断の軸が変わります。
ここから先は、いまの時期に合わせた考え方と、直前期の親の関わり方をまとめた記事に続けます。
▷【1月のC判定】下げる?挑戦する?出願前の判断ポイントはこちら
-

-
【都立】VもぎC判定は厳しい?
出願前に迷わない現実ラインと親のサポート続きを見る
▷ 受験直前、親が不安になる理由と関わり方の線引きを整理したい方はこちら
-

-
中3の冬に親が不安になるのはなぜ?
知っておきたい受験の現実続きを見る
▷ 直前期にやってよかった/やらなくてよかった親のサポートはこちら
-

-
【冬休み〜1月】中3受験直前
親は何をすればいい?
やってよかったこと・やらなくてよかったこと続きを見る
都立第一志望×私立併願のバランスがカギ!

「もし都立がダメだったら、どこに行く?」――ここを明確にしておくと、出願直前でブレにくくなります。
都立を第一志望にするなら、私立併願の位置づけを明確にしておくことがとても大切です。
以下の3パターンで考えると整理しやすいです
- 併願校にも行っていいと思える場合
→ 都立で少し上を狙ってもOK。チャレンジする余裕がある。 - 併願校にはあまり行きたくない場合
→ 都立は“確実に合格できるレベル”にしておくことが安心。 - どちらにも決めきれない場合
→ どちらにも進めるように、内申をキープしておくのが理想。
内申が1つ下がるだけで、併願優遇が取れないこともあります。
「この内申なら、ここまでの学校が併願で取れる」
という情報は、秋のうちに塾や学校で確認しておくと安心です。
そして、併願校を「どうせ行かないから」と軽く見ないこと。
実際、都立が不合格で私立に進む子は毎年います。
「行くことになっても納得できる学校」を選んでおくのが大切です。
▷都立か私立か迷っている場合はこちらの記事をどうぞ
-

-
【中学生 高校受験】都立か私立か?
子ども基準で選ぶ志望校の決め方続きを見る
親の関わり方で結果が変わる、出願前の心構え
1月が近づくと、Vもぎの結果や学校からの内申点が出そろい、親子ともに気持ちが揺れる時期です。
「どこを受ける?」「下げる?」「このまま行ける?」――そんな会話が増えてくる頃。
でも、この時期の声かけひとつで、子どもの気持ちは大きく変わります。
ここでは、出願前に親が意識しておきたい関わり方を2つの視点からまとめます。
「下げる判断」は失敗じゃない。責めずに受け止めて
1月のVもぎで現実を見て、どうしても下げざるを得ないケースがあります。
ここで親が気をつけたいのは、「頑張らなかったから下げることになったんでしょ!」と責める言葉を言わないこと。
実際、受験期に成績を上げるのは本当に難しいです。
内申も、みんなが努力している中で上がるのはごくわずか。
模試の判定だって、がんばりがそのまま数字に出るとは限りません。
子どもは、誰よりも不安を感じています。
「このままで受かるのかな」「下げたくないけどどうしよう」――心の中は焦りでいっぱい。
それを“やる気がない”と誤解されてしまうのは、とてもつらいものです。
どの学校でも、入学後に本人が頑張れば未来は変えられます。
都立でも私立でも、入った後の努力が本当のスタートです。
親はそのスタートを「よくここまで頑張ったね」と受け止めてあげてください。
「下げないの?」と急かすより、一緒に現実を見る
逆に、親が心配のあまり「下げたほうがいいんじゃない?」と何度も口にしてしまうケースもあります。
もちろん、経済的な理由や通学距離など現実的な事情があるなら、話し合いは大切です。
でも、「ただ不安だから」という理由で繰り返し言ってしまうと、子どもは「信じてもらえない」と感じてしまうことがあります。
出願直前の時期こそ、本人が自分で決めたという納得感が大切です。
たとえ結果がどうであっても、自分で決めたという経験が入学後の頑張りにつながります。
親は「どうするの?」と急かすより、一緒に現実を見るパートナーでいましょう。
安全校を“見学しておく”のが意外な安心材料に

志望校を下げるときに一番困るのが、「見たこともない学校しか残っていない」こと。
これは、毎年本当によくあるパターンです。
実際、12月~1月の出願直前になってから慌てて別の学校を調べ始めると、情報が少なくて不安になったり、「ここでいいのかな」と迷いが深くなってしまうこともあります。
だからこそ、秋のうちに安全校も2〜3校は見学しておくのがおすすめです。
いざというときに「ここなら通える」「雰囲気が合う」と思える学校があるだけで、気持ちがぐっとラクになります。
「安全校=行かない学校」ではなく、選択肢を確保する学校と考えるのがポイント。
見学しておくことで、下げる判断をする時にも迷いが少なくなります。
▷秋以降の高校説明会についての詳しい記事はこちらでどうぞ
-
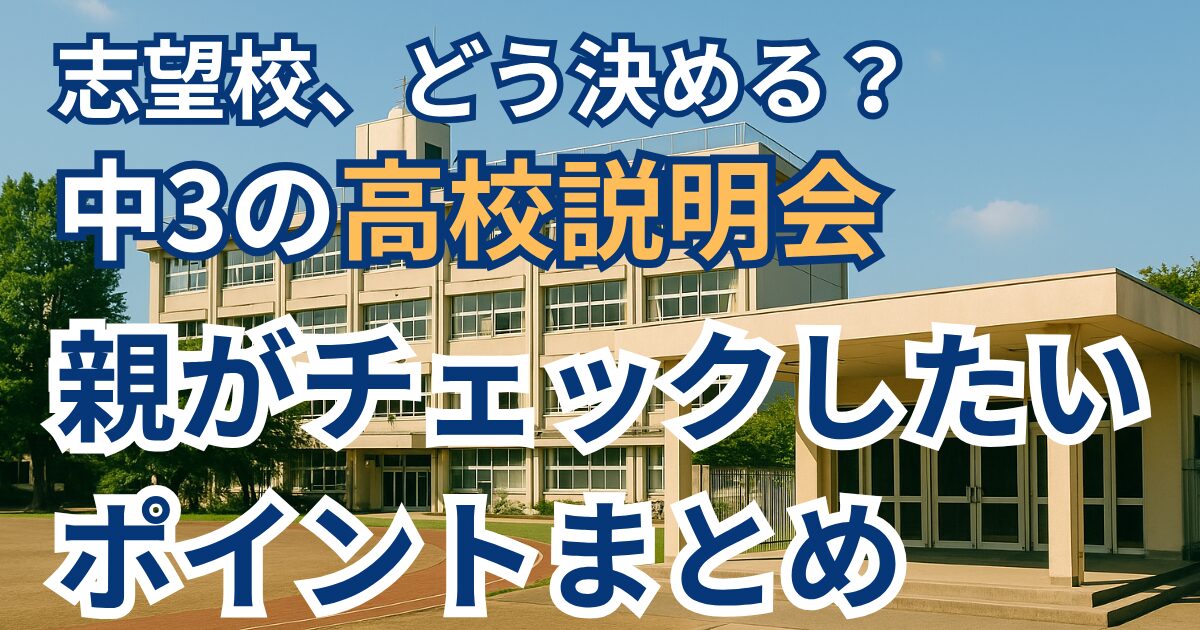
-
【中3秋】高校説明会で見るべきポイント
志望校を決める前に親が確認したこと続きを見る
受験は「うまくいくこと」より「立ち直る力」
ここまで、志望校の決め方と親の関わり方について整理してきました。
受験を経験した生徒をたくさん見てきて感じるのは、「うまくいったかどうか」よりも「その後どう立ち直ったか」が大事だということです。
最後にもう一度、親が意識しておきたいポイントをまとめます。
- 志望校は「今の実力」だけでなく、「入学後に通い切れるか」を基準に考える
- 都立第一志望なら、私立併願の位置づけを明確にしておくとブレない
- 「下げる判断」は失敗ではなく、次につながる選択と受け止める
- 「下げないの?」と急かすより一緒に現実を見る姿勢を大切に
- 安全校も2〜3校は見学しておくと、いざというときに落ち着いて判断できる
そして、12月後半〜1月の模試結果で不安が強いときほど、親がやるべきことは「勉強の管理」ではなく“段取りと空気づくり”です。
▷直前期の親の関わり方はこちら
-

-
【冬休み〜1月】中3受験直前
親は何をすればいい?
やってよかったこと・やらなくてよかったこと続きを見る
受験は結果よりも、その過程でどんな選択をしたかが大切。
都立でも私立でも、最終的に本人が納得して入学できれば、それが一番の成功です。
焦らず、見守っていきましょう。