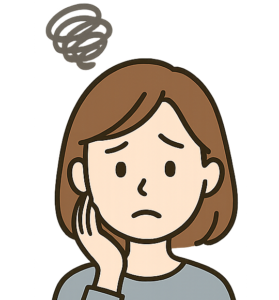
中2になってから、ちょっとずつ成績が落ちてきちゃった。
受験はまだ先だけど、このままだと危ないかも…。
でも、今からでも巻き返せる方法ってあるのかな?
「中2からじゃ、もう手遅れかも…?」
そんな不安を感じている親御さんへ。
中2は「中だるみの時期」とよく言われますが、実際には学校生活にも慣れ、友達や部活も楽しくなってくるぶん、勉強の優先順位が下がりやすい時期です。
「このままじゃ高校受験、大丈夫かな?」
「塾に行かせるべき?でも成績はまだそんなに悪くないし…」
そんなふうに迷っている方も多いのではないでしょうか。
私自身、塾講師として10年以上中学生を見てきましたが、この時期にほんの少し意識を変えるだけで、受験学年がぐっと楽になる子をたくさん見てきました。
この記事では、
- なぜ中2からでもまだ間に合うのか?
- 今日からできる受験準備のコツ
- 親ができる“ちょうどいい”関わり方
について、実体験を交えてわかりやすくご紹介します。

中2の勉強は「手遅れ」と言われやすい理由
「中1のころはまだ勉強してたのに、なんだか最近、うちの子…」
そんな風に感じている親御さん、いませんか?
実は、中学2年生って、親が思う以上に“勉強から気持ちが離れやすい”時期。
学校生活にも慣れて、毎日が楽しく充実しているからこそ、勉強への意識がゆるんでしまうのは、ある意味“自然なこと”。
ここでは、中2の子どもたちがつまずきやすい理由を、親の目線でわかりやすく整理していきます。
学校生活に慣れ、油断しやすい
中2は、クラスにも先生にもすっかり慣れて、友達関係も安定してくる頃。
部活や学校行事も楽しくなってきて、毎日が「まあまあ順調」に見える時期です。
でも実は、そこが落とし穴。
「成績もそこまで悪くないし、本人も元気そうだし」と油断しているうちに、知らない間に勉強への意識がフェードアウトしてしまうことが多いんです。
教科の難易度が上がる
中2の学習範囲には、入試に出やすい重要な単元がいくつかあります。
英語では “不定詞” や “受け身”、数学では “一次関数” や “図形の証明” といった抽象的な内容が出てきます。
もし中1の基礎がちょっとでも抜けていたら、「え?もうわからない…」と感じる場面が増えてしまうのも当然。
ここで自信をなくしてしまうと、ますます勉強が嫌になってしまうことも…。
親子関係も難しくなる時期
この時期の子どもは、いわゆる“反抗期まっただなか”。
親のアドバイスに耳を貸さなかったり、突然不機嫌になったり…。
何をどう言っていいのか、親も迷ってしまうことが増えますよね。
でも実は、本人も“ちょっと焦ってる”ことが多いんです。
うまくいかないことを自覚してるからこそ、
素直になれず、強がって見せているだけ…なんてことも。
だからこそ、親が冷静に寄り添ってあげることが大切。

なかなか冷静になれないんだけど…
「あっ、いま感情的になってる」って気付くだけでもOK!

中2からでもまだ間に合う!勉強習慣づくり

「このままで大丈夫かな…」と不安になっても、何から始めればいいのかわからない。
そんな親御さんも多いと思います。
でも大丈夫。
今から少しずつ動き始めるだけで、受験学年のスタートがグンと楽になります。
ここでは、「手遅れかも…」と感じている方にこそおすすめしたい、無理なく始められる勉強習慣づくりのヒントをお伝えします。
高校見学でやる気スイッチを入れる
もし、お子さんが「勉強したくない」「面倒くさい」と感じているなら、
それは“目標がまだ見えていない”からかもしれません。
中2の夏は、まだのんびりと高校見学ができるタイミング。
少しレベルの高い学校も含めて、実際に足を運んでみると、
「この制服いいな」「この雰囲気、好きかも」と、ふとした瞬間に興味がわくことがあります。
目標が見えると、人は自然と前に進みたくなるもの。
高校見学は、受験勉強の“スイッチ”を入れるきっかけになるかもしれません。
▷高校見学に関してはこちらに詳しく書いてあります
-

-
【体験記】高校見学で“見ておいてよかったこと・失敗したこと”を学年別に解説!
続きを見る
英検・検定チャレンジで自信をつける
英検や漢検などの検定にチャレンジしてみるのもおすすめです。
受験学年になってから慌てて取ろうとすると、プレッシャーも強くなりますが、今なら失敗しても大丈夫。
まずは英検4級から、少しずつステップを踏んでいきましょう。
試験に慣れておくことで、「本番で緊張しない力」も自然とついていきます。
何より「できた!」という達成感は、子どもにとって大きな自信になります。
▷英検に関してはこちらを参考に
-

-
中3で英検準2級に合格!1学期に受けてよかった理由と勉強スケジュール
続きを見る
自分に合った勉強スタイルを見つける
「机に向かわないと勉強じゃない」って、思い込んでいませんか?
実は、勉強のスタイルは子どもによってさまざま。
リビングで気楽に、図書館で静かに、自室で音楽を聴きながら──
どれも「本人が集中できるなら正解」です。
時間帯も、朝派・夜派・スキマ時間派とバリエーションは豊富。
ゲームの合間でも、お風呂上がりでも、やってみて「続けられそう」と感じるものを一緒に見つけてあげましょう。
“うちの子らしいやり方”を見つけることが、何よりのスタートになります。
▷勉強方法についてはこちらも参考にどうぞ
-

-
【保存版】中学生の自宅学習スケジュール|生活習慣から整える“勉強時間の作り方”
続きを見る
家庭学習の時間確保を“練習”する
勉強を習慣にするためには、「量」より「頻度」から。
まずは1日10分でもいいので、毎日ちょっとだけ勉強する時間を作る練習を始めてみましょう。
できれば、目に見える形で記録してあげると◎
たとえば、カレンダーにシールを貼ったり、アプリで学習時間を可視化したり。
ゲーム感覚で「続いてる!」という実感を持てると、子どもは自分から動きやすくなります。
勉強は“やる気”より“習慣”です。
最初の一歩は、小さくてOK!
▷家庭学習についてはこちらの記事をどうぞ
-

-
【中学生の塾に頼らない勉強法】家庭でできる高校受験サポート実例
続きを見る
「勉強手遅れ」を防ぐ!親のサポート法

勉強に向かうのは、もちろん子ども自身。
でも、その環境を整えたり、気持ちの切り替えを手伝ったりするのは、親にしかできないことです。
「何をどうサポートすればいいかわからない…」という方も、大丈夫。
ここでは、中2の子どもたちに“効く”親の関わり方を、無理なくできるものに絞ってお伝えします。
怒らず、責めず、一緒に取り組む
「どうしてやらないの?」「またゲーム?」
そんな言葉、つい口に出してしまったことありませんか?(私はたくさんあります…)
でも、実は子ども自身も「やらなきゃいけない」と思ってることがほとんどなんです。
ただ、うまくできない時や、自信がない時ほど、ついダラダラしてしまうのが子ども。
そんな時こそ、親が責めるのではなく、
「一緒にやってみようか」「今日はここだけでOKにしよう」と手を差し伸べてあげてください。
怒るより、“やり直せる空気”をつくってあげるほうが、ずっと効果的です。
信頼関係を育てる関わり方
中2の子どもたちは、もう「子ども扱い」されるのを嫌がる年ごろ。
でも、だからといって完全に放任してしまうと、心が離れてしまうこともあります。
大切なのは、“見守りつつ、必要なときには手を貸す”というスタンス。
「困ったらいつでも手伝ってあげるね」
そんなメッセージを、態度で伝えていくことで、
受験期の土台となる“信頼関係”が少しずつ育っていきます。
親も余裕を持って見守る
子どものことを心配するあまり、親がピリピリしてしまう…。
よくあることです。
でもそれ、実は子どもにも伝わっています。
だからこそ、まずは親自身が、ちゃんと自分の時間を持つことも大切。
家事をちょっと手抜きしたり、趣味の時間を確保したり、夜は早めに休んだり…。
「親が笑顔でいること」が、子どもにとっての安心につながります。
たとえば、子どもがAIで勉強スケジュールを立てるなら、親も一緒にダイエットスケジュールを作ってみるなど、
“親子で挑戦中”の雰囲気を楽しむのもおすすめ!
▷ 忙しい親の時間づくりには、こちらの記事も参考になります
-

-
夜家事ゼロを叶える!朝&日中のスキマ時間でできる時短テク
続きを見る
中2の“勉強手遅れ”を防ぐポイントまとめ

この記事のポイントをまとめました。
- 油断しやすい時期と理解する:学校や部活に慣れて勉強が後回しになりやすい
- 重要単元に注目する:不定詞・一次関数など受験で必ず出る内容を押さえる
- 高校見学で目標を見つける:やる気のスイッチは「将来をイメージできるか」
- 検定チャレンジで自信をつける:英検や漢検で「できた!」を積み重ねる
- 自分に合う勉強スタイルを探す:リビング学習や夜派など“続けやすさ”を優先
- 親は責めず、環境を整える:一緒にやってみる姿勢が効果的
中2からでもまだまだ巻き返せます。
親子で一緒に「できることから始める」ことが、一番の近道です。
