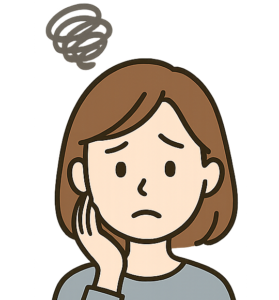
うちの子、帰ってきたらグダグダしてて全然勉強しない…これでいいのかな?
「こんなに勉強のやる気がなくて、ちゃんと高校に行けるの?」
「宿題があってもゲームやスマホを見てばっかり…」
そんなふうに不安を感じているご家庭、多いのではないでしょうか。
実は、勉強する・しないの差は、「やる気」だけの問題ではありません。
大切なのは、毎日の生活の中に勉強に向かう流れが自然と組み込まれているかどうかです。
私は塾講師として10年以上中学生を見てきましたが、家でしっかり学習できている子には、ある共通点がありました。
それは、生活習慣が安定していること。
といっても「毎日決まった時間通りに!」なんて難しいことはできませんよね。
ご飯・お風呂・寝る時間が「だいたい」決まっていて、
その中に無理なく勉強に向かえるタイミングがある、それだけで十分です。
実際、わが家も毎日うまくいっていたわけではありません。
それでも、ある程度の流れを決めていたことで、子どもたちも自然と勉強に取りかかりやすくなっていました。
今回は、そんな“無理なく続ける家庭学習の仕組み”を、実際のスケジュール例とともにご紹介します。

中学生の勉強時間はどれくらい必要?【理想と現実】
まず気になるのが「いったい1日どのくらい勉強すればいいの?」という疑問。
理想を言えば…平日も休日もそれぞれしっかり1〜2時間、テスト前には3〜4時間やってほしい!
でも、実際の中学生の生活ってほんっっとうに忙しいですよね。
- 部活がある日は帰宅が18:30頃
- 夕食・お風呂・宿題を終えるだけであっという間に21時
- 塾に行っていれば、帰宅は22時以降
そんな中で、「毎日3時間勉強しよう!」なんてなかなか難しい。
でも大丈夫。大事なのは毎日コツコツやる仕組みを作ること。
いきなり長距離を走るのは難しくても、毎日1kmずつ走っていれば、いずれ10kmも走れるようになる。
勉強も同じです。
勉強が続く家庭の共通点は「生活習慣」にあった!

自宅学習がうまくいく家庭とそうでない家庭、その違いは勉強そのものよりも生活の流れにあります。
生活リズムを安定させる
- 「帰宅 → お風呂 → 夕食 → 勉強 → 就寝」の流れができている
- スマホの使用時間にルールがある
- 毎日、勉強に向かう“タイミング”がだいたい決まっている
- 子ども自身がやるべきことを把握している(学校の宿題・検定の勉強・テスト対策など)
これだけで、家庭学習の安定感はぐんと変わってきます。
▷家のスケジュールを整えるには、親の朝の動きもポイント。
-

-
家事が苦手でも大丈夫!
朝10分で夜がラクになる私のやり方続きを見る
家庭学習スケジュール例【平日・部活がある日】
部活がある日は帰宅が遅く、夕食やお風呂であっという間に夜の時間が過ぎてしまいます。
そんな中でも無理なく勉強の時間を確保するには、「夕方から寝るまでの流れ」をざっくり決めておくのがポイントです。
以下は、わが家で実践していたある日のスケジュール例です。
もちろんこれは一例なので、お子さんの活動や家庭の状況に合わせて調整してみてくださいね。

家庭学習スケジュール例【平日・塾がある日】
塾がある日は帰宅も遅くなり、勉強時間を確保するのはさらに大変。
この日は無理に家庭学習を詰め込まず、塾で学んだことを「その日のうちに終わらせた」という達成感を大事にする日として割り切るのも一つの方法です。
こちらは、塾がある日を想定したスケジュール例です。
塾の時間帯やお子さんの疲れ具合に応じて、必要に応じて調整してみてください。

▷テスト直前はまた別のスケジュールが必要になります。詳しくはこちらの記事をどうぞ。
-

-
【定期テスト前】やる気ゼロな中学生に
親ができる声かけ&環境づくり7選続きを見る
家庭学習が続く仕組みづくり|親ができる5つのコツ
「どうしたら家でちゃんと勉強してくれるの?」
そんな悩み、きっと多くのご家庭が感じていると思います。
でも実は、気合いや厳しさよりも、仕組みのほうが何倍も効果的。
家庭学習が自然と続くようになるには、子どもが「やってみようかな」と思える環境と流れを整えてあげることが何より大切です。
ここでは、私が実際に子どもたちと関わる中で感じた、家庭でできる続ける仕組みのコツを5つご紹介します。
① 勉強場所は自由でOK!やりやすい環境を整えて
リビングでも自室でも、本人が落ち着けて集中しやすい場所ならどこでも大丈夫。
大切なのは「どこででも勉強に取りかかれる環境を用意しておく」こと。
- どの部屋でもノートやワークを広げられるスペースを空けておく
- 筆記用具をいくつか準備しておいて、いちいち探さなくてもいいようにする
「机にまっすぐ座って、静かに勉強しなきゃいけない」なんてことはありません。
寝そべっててもいいし、立っててもいい。本人が学べていれば、それが正解です。
▷寒い季節に勉強の集中力を上げるあったかグッズは、こちらの記事にまとめています。
-

-
【中学生の集中力を上げる!】
冬にほんとに役立った
あったか勉強グッズおすすめ続きを見る
② 子どものスイッチを一緒に探す
勉強に入りやすいきっかけ(=スイッチ)は、本当に子どもによって違います。
- 座る場所を決めると集中できる
- ノートを開くとスイッチが入る
- とにかく“好きな教科”から始めると気持ちが乗る
- 逆に“嫌いな教科”から片づけてスッキリしたい子も
中には「まず宿題を終わらせないと落ち着かない」というタイプもいますし、
「とりあえず漢字だけやる」「英単語だけ書く」など、ちょっと始めることで動き出せる子も。
親が一緒に探って、「うちはこうするとやりやすいね!」と気づいてあげられると、習慣化がスムーズになります。
③ くつろぎ時間も肯定して、ルールは親子で決める
子どもがリビングでのんびりしていると、「いつになったら勉強するの?」と言いたくなる気持ち、すごくわかります。
でも、ルールさえ守っているなら、自由時間も大事にしてOK。
たとえば「スマホは22時まで」と決めたら、それまではとやかく言わない。
その“自由とルールのバランス”が、親子関係を壊さずに学習習慣を作るコツです。
親が「リビングでくつろぐ=サボってる」と決めつけると、子どもは安心して過ごせる場所がなくなり、自室にこもるようになってしまうことも。
まずは「見守る姿勢」が、信頼感を育てます。
④ 要領よくやることを教えてあげる
真面目な子ほど、
- わからない問題に何十分も悩む
- 1ページを1時間かけてしまう
- 細かい部分にこだわりすぎて前に進まない
…ということがよくあります。
今の時代は、「まず終わらせる」→「あとで見直す」という流れがとても大事。
特に時間が限られる中学生には、完璧を目指しすぎないことも実力のひとつです。
親が「そこは飛ばしていいよ」「今は答え見て大丈夫」と声をかけてあげるだけでも、
子どもの気持ちはぐっとラクになります。
⑤ 立ち止まらず、調べたり聞いたりできる力を育てる
「この問題、全然わかんない…」と止まってしまうと、気持ちも一気に落ち込みますよね。
でもそれ、今の自力ではわからなくて当然なだけかもしれません。
そんなときは、
- 答えを見る
- 印をつけてあとで聞く
- 調べて自分で解決する
…など、止まらずに進む手段を持っておくことが大事です。
「今考えてもわからないなら、今じゃなくていいよ」
そう言ってあげられるのが、家庭学習を支える親の一番の役割かもしれません。
▷提出物が出せない子おすすめの記事はこちら。
-

-
提出物を出さない中学生に悩む親へ!
怒らずできた3つのサポート法続きを見る
教材は“完璧”より“やる気と相性”で選ぼう

「市販の問題集、何を買ったらいいか分からない…」
そんなふうに悩んでいる親御さんも多いと思います。
でも実は、「内容が良い教材」よりも「本人がやる気になる教材」のほうが圧倒的に効果があります。
どんなに有名な参考書でも、開かなければ意味がありません。
逆に、少しレベルが低くても「これならやれる」と思える教材の方が、確実に力になります。
ここでは、家庭学習をサポートする教材選びのポイントを6つご紹介します!
学校の課題が最優先!
市販教材を使う前に、まず優先すべきなのは学校のワークやノート、宿題。
これらは提出状況がそのまま通知表の評価に直結することも多く、やっていないと評価が下がる可能性もあります。
また、学校で使っている教材は教科書に沿った“教科書準拠”の内容なので、定期テストにも出やすく、基礎力をつけるのに最適です。
市販教材はあくまで補助的なもの。
まずは学校の課題をきちんとこなしたうえで、必要に応じて活用するのがおすすめです。
やる気が出る教材が最強!本人がこれならできそうと思えるものを
教材を選ぶときは、「親がいいと思うもの」ではなく、「本人がやってみたい」と思えるかどうかが重要です。
- 本人にとって、やりやすく見やすいレイアウト
- 1日10分、1回○ページなどの具体的な進め方が載っている
- やさしめの問題から徐々にステップアップする構成
…など、「とっつきやすさ」を重視しましょう。
実際に中身を見せて、「これならできそう?」と一言聞いてみるだけでも、やる気の出方が変わります。
▷わが家で本当に役に立った中学生向けの勉強グッズは、こちらでまとめています。
-

-
中学生の勉強がはかどる!
本当に使えるおすすめ勉強グッズ8選続きを見る
難しすぎない!自力で解けるレベルから始めよう
「これ、難しすぎて自分じゃ無理…」と思ってしまった瞬間、子どもはその教材を開かなくなります。
おすすめは、理解度8割くらいのもの。
多少わからない問題があっても、「がんばれば自分で解ける」と感じられるものが◎。
もし今の学年の内容が厳しければ、前の学年に戻ってもOK!
できるところからスタートして、「わかる」→「できる」→「おもしろい」の流れをつくってあげましょう。
すべてやらなくていい!使い方で工夫しよう
教材って、買うとつい「全部やらせなきゃ」と思ってしまいがち。
でもそれは子どもにとってはプレッシャーにもなります。
- まずは各単元の基礎問題だけやる
- 時間がないときは1日1ページだけにする
- 「できるところだけやる」でOK
使い切るより使い倒すくらいの感覚で十分!
本人が「これなら続けられる」と感じる進め方で、無理なく学習習慣をつけていきましょう。
プリント学習は取り組みやすく、効果的!
「問題集を1冊やりきるのが苦手」「何ページもあるとやる気が失せる」
そんな子には、1枚で完結するプリント学習がぴったり。
- 教科書準拠の無料プリントをネットから印刷
- 問題集のページをコピーして書き込み用に使う
- テスト対策の小テストを親が作ってもOK
1枚終わるたびに達成感が得られるのも、プリント学習のメリットです。
プリンターがあると家庭学習がはかどる!
プリント学習やワークのコピーを活用するなら、家庭用プリンター&コピー機があると本当に便利。
- ワークをコピーしてテスト前に繰り返し使える
- ネットで見つけた問題をすぐ印刷できる
- 小テストや英単語テストもサクッと作れる
カラー印刷にこだわらないなら、レーザープリンターが圧倒的に便利!
最近のレーザープリンターはコンパクトで低価格です。
“勉強環境のインフラ”として、1台あると大きな助けになりますよ。

我が家で使っているのはこの複合機です
◆まとめ|「できる時間で、できる方法で」続けるのが家庭学習のコツ!
中学生の家庭学習は、「やる気」や「時間の長さ」だけでなく、生活習慣や環境の整え方がカギになります。
- 帰宅後の流れを決めておく
- 勉強場所ややり方は“その子に合う形”で柔軟に
- 教材は「本人がやる気になるもの」を選ぶ
- 学校の課題を軸に、プリントやコピー学習も活用
どれも特別なことではありませんが、毎日少しずつ積み重ねていくことが何より大事。
完璧を目指さず、家庭に合った方法で“続けられる仕組み”を作っていきましょう!

